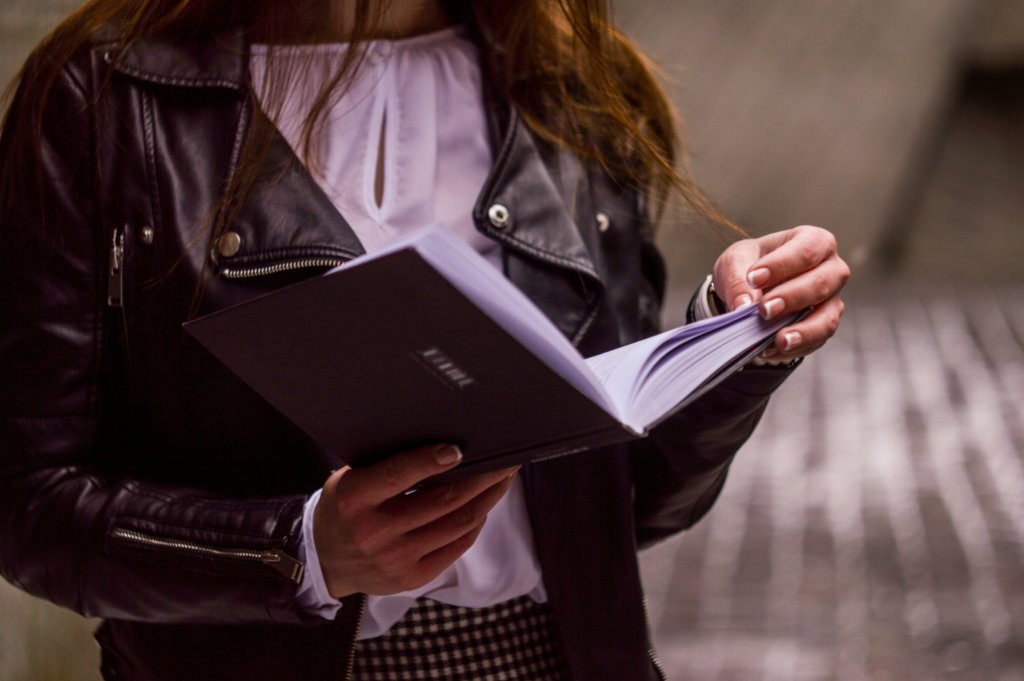巨匠成瀬巳喜男の遺作に刻まれた女の情欲の影
日本が世界に誇る映画監督の中で、溝口健二、小津安二郎、黒澤明に続き「第四の巨匠」と呼ばれている成瀬巳喜男の評価は国内外において、年々高まるばかりです。
 パドー
パドー1969年に63歳でこの世を去った成瀬の遺作が67年に公開された本作「乱れ雲」となります。
「乱れ雲」というタイトルは、女主人公の揺れ動く心情を象徴しています。
以下にその「雲」の最後の「動き」についての考えを記します。内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。
あらすじ
妊娠中である江田由美子(司葉子)は、通産省勤務の夫の宏のアメリカへの栄転が決まり、赴任を控え準備に忙しくなる矢先、夫が交通事故で死亡する知らせを受ける。加害者である商事会社勤務の三島史郎(加山雄三)は裁判の結果、無罪となるが、道義的呵責から毎月由美子にお金を送り続け、償いに務めている。流産の後、夫の両親から戸籍を抜くように執拗に迫られ、遺族年金の受け取りの権利も消失した由美子は姉の文子(草笛光子)のすすめもあって、経済的な理由から亡き兄の妻である四戸勝子(森光子)が切り盛りする青森県の実家の旅館に世話になることを決意する。一方、史郎は常務の娘との婚約も解消となり青森に左遷されるが、偶然に彼の地で由美子と再会することとなる。やがて愛憎がもつれあいながら、互いに惹かれ合う気持ちを確認するも、史郎が駐在先としては最悪の部類に入る海外のラホール(パキスタン)に赴任することを機に、結ばれることなく別れに至る。
メロドラマの体裁をとったとしても
多くの評論の通り、本作は典型的なメロドラマのスタイルをとっています。
繊細なタッチを特徴とする成瀬には珍しく、メロドラマであるために、物語の展開上、ご都合主義が前面に出ています。
メロドラマとは、ご都合主義的であり、扇情的であり、通俗的であり、感傷的なスタイルが特徴です。
最初から最後まで、物語は偶然の連続に終始します。
成瀬のきめ細やかな演出を期待する者のうちには、このようなメロドラマ性を嫌う者も少なからずいるかもしれません。
ご都合主義に堕したということは簡単です。
あなたが観るべきは「愛憎の間を揺れ動く女心」に他ならないのです。
そのための舞台としてごく自然に「メロドラマ」が採用されていること理解するならば、低評価を下すことはお門違いというものでしょう。
成瀬映画を象徴する「チンドン屋」と「お金の事」はスクリーンから後退します。お金が大事だという台詞が消えることはないのですが、主人公が「お金の問題じゃない」という啖呵に世相を反映した成瀬の変化が見て取れます。
「乱れ雲」とは
繰り返しになりますが、
「乱れ雲」とは、加害者の史郎への憎しみの気持ちとその逆に彼に惹かれざるを得ない愛する気持ちの間を揺れ動き、乱れていく由美子の心情を象徴したタイトルとなります。
すなわち、ここで描かれているのは、女心であり、男である史郎の気持ちでは全くありません。
なぜなら、史郎は決してこころ乱れないからです。
本作においては、乗用車とボートは不吉の象徴であり、常に死の影をまとっています。一方、バスと列車は希望の予感に満ち溢れた乗り物であると言えるのです。
史郎という男の乱れない心
正義感に溢れ、愚直すぎるキャラクターである史郎という人物は、それでは恋愛に関しても不器用で鈍感であるかと言えば、実はそうではありません。
できる商社マンであることを念頭に置けば、人の気持ちについての感度は当然に良好であると言えます。
恋愛に関しては、むしろ敏感にすぎるぐらいに敏感であり、空気が読めるのです。
劇中において、彼は三度、「情事の予感」を意識的に排除します。
それが「自然」と映るのは、彼の「技巧」の賜物であるのでしょう。
- 婚約者の淳子(浜美枝)との自分のアパートでの別れの場面
- 営業所内の女性社員からの送別会後の二人だけの誘いを煙に巻く場面
- 由美子と旅館に行った時に彼女とここで関係を持たないと暗示する場面
抑制の理由はともかく、彼は自制心をいつ何時も働かせ、乱れることも揺れ動くこともありません。
ひとつひとつ見ていきましょう。
勝子(森光子)の得体の知れなさは尋常ではありません。女将同士の集まりで「どじょうすくい」を嬉々として踊る横で、見ず知らずの女将から夫が事故で亡くなったことを同情される由美子の当惑。もちろん勝子が言いふらしているからに他ならないのですが、その太々しさが踊りのシーンに間接的に凝縮されています。見事すぎる演出。
婚約者の淳子(浜美枝)との自分のアパートでの別れの場面
会社での常務とのやりとりの後、失意の中、彼は自分のアパートに戻ります。
そこにはいつものように部屋の片付けを終えたばかりの婚約者の淳子がいました。
彼女は言います。
「青森には行けないわ。お父さんに言われたからじゃないの。自分で決めたのよ。ごめんなさい。」
自己保身の塊のようなセリフは底冷えのする冷たさをあたりに漂わせます。
極めて打算的なセリフのあと、窓の外にサイレンが遠く聞こえ、淳子は窓を閉め、カーテンを引きます。
このシーンに続き、史郎の当惑の表情のアップとなります。
ご承知の通り、
この一連の動作の意味するところは、あなた(史郎)と一緒にはなれないと口にはしたが、今ここで「抱いてください」という暗黙のメッセージが淳子から放たれているのです。
そんなことはできないというメッセージは、再びカーテンを引き、窓を開ける史郎の行為により表現されます。
彼の意思を明確に理解した淳子はなにも言わず、白いハンドバックを手に取り、黙って出ていきます。
 パドー
パドーハンドバックの下に合鍵が置かれている演出がなんとも心憎いです。
ここで見逃してはならないのは、淳子が史郎を「試している」ということです。
私の気持ちは伝えたが、それでも私の心を変えたいのならば、私を「愛して」翻意させてみなさいと訴えているのでしょう。
彼は、このこともしっかりと認識した上で、明確に「ノー」を突きつけたのです。
「白い」ハンドバックにおけるカラーメッセージは二重性を帯びています。ひとつは、もう一度ここから二人の関係性を築いていきましょうという「原点」を示していると同時に、もうひとつは、それが叶わなかったので、あなたとの関係は「白紙」になりましたという意味なのです。
営業所内の女性社員からの送別会後の二人だけの誘いを煙に巻く場面
赴任早々から、明らかに史郎に好意を寄せていたと思われる若い女性社員は、営業所内の送別会の後に二人だけでどこかに行かないかと誘いの言葉を投げつけます。
彼女の意図を的確に理解している史郎は、彼女を傷つけないように、聞こえなかったふりをして、用事を言いつけ、その場を収めます。
彼の実直な人柄が現れていると同時に、関心のない対象には一切の興味を示さないブレのなさが強調された演出であると言えます。
由美子と旅館に行った時に彼女とここで関係を持たないと暗示する場面
裏山での告白の後、キッパリと由美子から断られ、諦めていたはずの史郎の元に由美子が訪ねてきます。
訪問の「意味」を知った史郎は、由美子と愛を確かめ合うために、一路旅館へと向かいます。
道中、車同士の交通事故を目撃し、旅館に到着後、窓の外に負傷者の男性とその妻が救急車に乗り込む場面を認めた二人は、不意に忌まわしい過去の記憶にがんじがらめにされて、情事への気持ちが暗礁に乗り上げます。
由美子の「ごめんなさい」という言葉を耳にした直後に中居が部屋にお茶を持って入って来ます。
「お風呂へどうぞ」という問いかけに対して、史郎は一瞬のためらいのあと「すぐ食事にしてください」と吐き捨てます。
その言葉を耳にした由美子が史郎を仰ぎ見るクローズアップののち、食事が運ばれたあと気まずい雰囲気が二人を囲っているシーンが重なります。
この仰ぎ見る由美子の表情に「なに」を読み取るかがポイントとなります。
本作は、女優司葉子の美しさを堪能するための映画であると言い切れます。とりわけ彼女の表情の豊かさは映画を観ることの至福のひとつに数え上げられるでしょう。特に、裏山で山菜を取っている時に不意に史郎から声をかけられ驚いたときの神々しさ。また史郎に思わず会いに行ってしまった時に、階段の下から史郎を仰ぎ見たときの恥じらいの微妙さ。そのふたつに匹敵するのが、ここで取り上げている旅館での史郎を見上げる複雑な表情であるのです。
相似形より構造的に読み説く
先に触れました婚約者の淳子との別れの場面と、ここでの由美子とのシーンを比較してみてください。
演出の意図は明らかに相似であることを示しています。
- 窓の外でサイレンが鳴っている
- 女性の方から「ごめんなさい」と拒絶がある
- 男の側(史郎)に次の行動の選択権が委ねられている
サイレンとは文字通り、警告であり、これから注意し、集中しなければならない「時」が訪れることの前触れを意味します。
「ごめんなさい」という発語は、あなたの意に即すことができないことを示す意思の表れです。
それを受けて、次のアクションをどうすべきかが史郎に求められているのです。
相似形をなしているということは、淳子の行動・意図から類推するに、史郎を仰ぎ見ている由美子の心情は、淳子と同等でなければならないことを意味します。
すなわち「抱かれること」を由美子も欲しているのです。
単純に恋愛の昂りが萎えたと解釈して済ますほど、成瀬の演出は「野暮」ではありません。
涙の背後で試しているのです。
夫の交通事故死という消し難い過去を乗り越えてでも、私(由美子)を愛し続けることができるのかを史郎に問うていたのです。
彼の出した答えは「風呂に入る(寝床への前章)」のではなく「食事」でした。
あなたは、彼の「答え」に対する失望と安堵が入り混じった心情の揺れを由美子の表情に認めるべきなのでしょう。
ここに「雲」の最後の最後の「乱れ」があったに違いありません。
ただのメロドラマではない
成瀬が本作で描きたかったのは、単なるメロドラマ上の女心ではなかったはずです。
女の情欲の影を表現したかったのでしょう。
女の情欲は、ある意味、義理の姉である勝子(森光子)を通じて縦横に表現されています。
そうではなく、
湖の水面に揺らめく人影の如く、情欲の「影」を演出したかったに違いありません。
「影」とは実体でないにも関わらず、実体以上に実体を感じさせる存在性を有したものです。
その期待に十二分に応えた司葉子は、紛れもなく成瀬映画の「実体」を象徴する存在でありました。
ここから司の「影」は独り歩きをし、彼女の演技は一皮も二皮も剥け、輝いていったのです。
成瀬が長生きしたのならば、高峰秀子とタッグを組んで作り上げた映画史に残る作品を同様に司葉子とも築いていっただろうと想像するに、本当に惜しまれます。