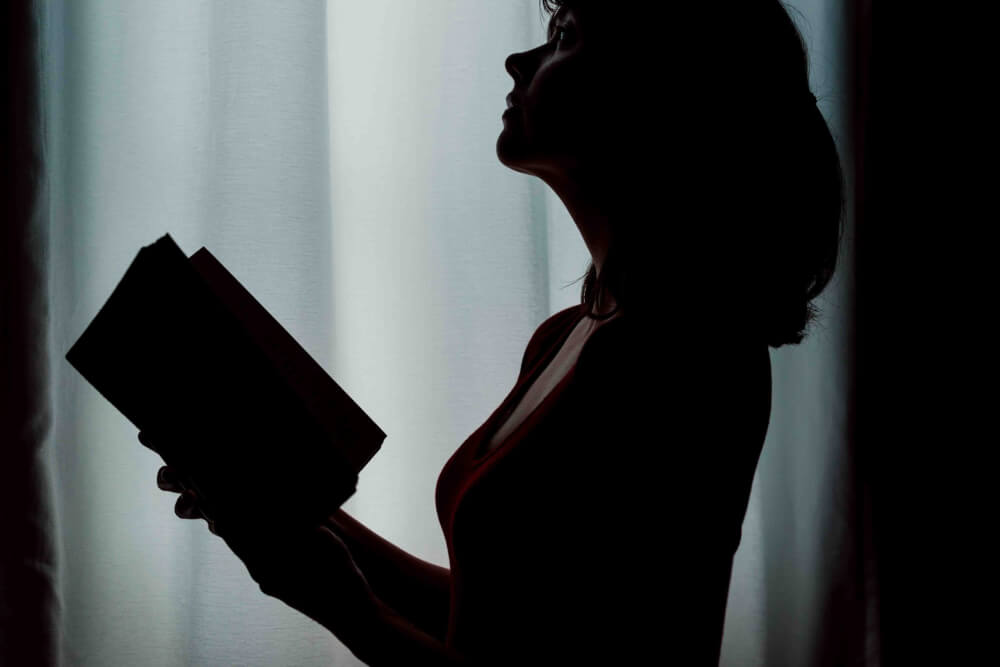極めて寡作な漫画家の極めて叙情的な傑作
アフタヌーン四季賞夏のコンテストにて大賞を受賞しデビューした豊田徹也氏の現時点での唯一の長編作品である本作「アンダーカレント」は、2004年より講談社アフタヌーン誌に連載され、2005年に単行本化されました。
 パドー
パドー受賞作「ゴーグル」は、敬愛する審査員の谷口ジロー氏より絶賛されました。
本作以外に現在、まとまって読める彼の作品集は「ゴーグル」と「珈琲時間」の二作のみです。
アンダーカレントという語の意味は単行本の見開きには次のように解説されています。
- 下層の水流、底流
- 《表層の思想や感情と矛盾する》暗流
本作は、ビル・エヴァンスとジム・ホールによる『Undercurrent』からインスパイアされている(タイトルと表紙は言うに及ばず)であろうことは多くの方が指摘する通りでしょう。
ジャケットを見て直ちに思い起こされるのは、シェイクスピアの戯曲「ハムレット」の劇中人物オフィーリアを描いた、ジャン・エバレット・ミレーの絵画『オフィーリア』です。彼女が溺れる前の、歌いながら川面に浮かぶ姿を描いている神秘的な作品となります。
良質な映画のようだと形容され、熱狂的なマニアを持つ本作について、以下に思うところを書き記します。
 パドー
パドー内容に言及しますので、あらかじめご了承下さい。
ストーリー
銭湯「月の湯」を経営していた関口かなえのもとから夫の悟は突然姿を消します。失踪後、叔母と共に営業を再開しますが、人手不足のため、組合の紹介により経験者である堀を臨時に雇用することになります。友人の勧めにより探偵を雇い夫の捜索を依頼するも、調査が進むにつれて、かなえの知らない夫の秘密が少しづつ明らかになっていくのです。
物語は、焦らず、弛まず、非常にいいテンポで流れます。
セリフのあるシーン、セリフのないカットが効果的に配置され、作品に奥行きを与えます。
 パドー
パドーおそらく、これまでに幾度も映画化の話が持ち上がっている(た)であろうことは容易に想像できます。
 パドー
パドー2023年10月6日、今泉力哉監督・真木よう子さん主演にて劇場公開されました。これは見ないといけない
本作を語る時に口にされる「まるで映画のようだ」という言葉を耳にするとき、映画表現とマンガ描写が相互に影響を与え合う関係にあることが思い起こされます。マンガは、構成やカット割り、アングルなど多くを映画から学びましたが、マンガが映画の表現の幅を広げてきたのもまた事実です。日本のマンガで言えば、手塚治虫氏や大友克洋氏の作品が直ちにあげられることでしょう。大友作品である「童夢」はその代表例であると言えます。
かなえという暗流
本作のタイトルである「アンダーカレント」とは第一に、かなえその人を指しています。
彼女が見せる「水面」と彼女が抱える「暗流」は全く違う顔を持ちます。
- 明るくて本当に元気
- なんでも一人でできちゃう
- しっかり者で気が強い
このような世間の評価(水面)と自身の内実(暗流)のギャップをかなえはきちんと自覚しています。
なぜなら、彼女がそのように演じてきたからです。
彼女には決して他人に言えない過去があります。
子供の頃、誘拐されそうになった自分を助けようとした友達のさなえが逆に連れ去られてしまいます。
誘拐犯はかなえに対して「誰にもいうんじゃないぞ!いったらお前を殺すぞ!!いつまでもお前を見ているからな!!」と脅し、恐ろしさのあまり、友達のさなえのことに関して一切口を閉ざしてしまうのです。
捜査の甲斐なく、さなえは近くの池で首を絞められた溺死体として無残にも発見されます。
物語の中では直接的には言及されていませんが、かなえが連れ去られた状況を即座に周りの大人に話していたのならば、事件は悲惨な結末を迎えなかったのかもしれません。
その後の人生において、かなえは自分の代わりにさなえが死んでしまったという罪悪感を背負い続けます。
ゆえに「明るく元気で大人たちに好かれ、短い髪の似合ったさなえちゃん」を演じてきたのでしょう。いや、演じざるを得なかったのです。
彼女になろうとすることで彼女の生を継続させ、罪滅ぼしを果たそうと、そのように生きてきたに違いありません。
私は長い間 さなえちゃんの かわりを生きてきた
死ぬこともできずに
「わたしが死ねばよかった」という後悔に苛まれながら、毎日を「明るく元気に」演じることが、どれほどの「地獄」であったかはもはや言うまでもないでしょう。
彼女が絶望から自死を選ばないのは、そうすることにより「かなえの人生」を確実に終わらせてしまうからに違いありません。それはなんとしても回避されなければならないのです。
実家が銭湯であるため、「たくさんの水」を日常的に目の当たりにし、嫌でも最期の池を連想せざるを得ないのが彼女の「日常生活」だったと言いえます。ある意味、生き地獄を生きるのです。
市井の人々の癒しの場である銭湯は、彼女にとっては忌まわし過去を思い出させるだけの「特異な場所」でしかないのでしょう。
少なくない年月が経ち、生々しさは軽減されたものの、全てが消え去ることは決してありませんでした。
そのために、水の中で首を締められる夢を幾度となく見てしまうこととなります。
堀に対する自己紹介の際にかなえは「関口かなえ」と名乗ります。物語の後半の回想シーンにおいて悟は「白石悟」と名乗っています。最後に離婚届を送るやりとりが二人の間で交わされていることから、推測するに悟は婿養子に入ったと思われます。仮にそうであるならば、彼の嘘で塗り固めた人生の「変容性」がここでも示されていることと言えるでしょう。
流れの中の3つの層
先ほど、「アンダーカレント」とは第一にかなえを指すと言いました。
本作は「暗流」を3つの層(心層)にグラデーションしています。
「かなえ」/「堀」/「悟」です。
かなえの場合は先にみたように、表層と深層がきれいに別れていて理解しやすい構造となっています。
堀の場合は、ある種の中間層と言えます。
悟の場合は、表層と深層の境がもはや確定できません。
以下に、男性二人の場合をみていきます。
豊田氏の絵のタッチやテイストに対して谷口ジロー氏の影響を指摘する論はたくさんあります。私の場合、すぐに思い浮かんだのが、佐藤宏之さんと吉田秋生さんです。作中のサングラスの二人の男、探偵の山崎と近所の変わり者の爺さんである田島三郎(通称サブ爺)は、佐藤氏の作品の中に登場していても、なんらの違和感のないキャラクターであると思います。
中間層としての堀
堀は、殺されたさなえの実兄です。
彼は長い間、子供時代に過ごした街を離れていましたが、仕事で偶然に立ち寄ることになり、そこで散歩中のかなえを見かけます。
彼女に対する関心が高まり、銭湯で働くこととなりますが、彼自身、何を目的として彼女に近づいているのかの明確な理由を見つけることができません。
・・・なんのためにここに来たのか自分でもよくわからないんですよ
彼女のことを妹だと思ったわけではありませんし
ぼくのことを気がついてほしいと思ったわけでもないんです
だいたい彼女はそんな昔の事件のことは忘れているように見えました
・・・でも違う 忘れてなんかいない
彼女はずっと傷ついて苦しんできたんだと思います
ここで語られているのは、心層における表層と深層が互いに侵食し合い、本心が希釈された状態です。
「本心」は立脚点を失い、理由や根拠はどこまでも漂流しています。
物語の中盤で挿入されている下着泥棒の少年のエピソードは2つのことを示唆しています。ひとつ目は、罪が明るみに出ることがどれほど本人にとって救いとなるかです。これによって、かなえや悟の心の闇の深さに光があたります。二つ目は、人は自分の行動を制御できないという性(さが)です。悟の虚言癖に対する前振りのような役割をこのエピソードは帯びていると言えます。
表層も深層もない悟の場合
ウソが口を突いてしまう悟は、彼が作り上げた虚構の体系に綻びが出るたびに、人間関係を精算し、知らない土地へと移動(逃避)を繰り返します。
人は「本当のこと」など断じて知りたくはないという「悟り」に従い、心地のいいウソを提供し続けます。
その結果、彼は自分の表層と深層の判別が不可能となります。
それは同時に、他人(相手)の心の表層と深層の境を見失うことを意味します。
なぜなら、相手の深層は自分が差し出した表層に他ならないからです。
表層と深層の区別がつかないとは、全てが真実であり、同時に全てが虚偽である混沌を指します。
そこは、「意味」が分解している世界なのです。
物語を駆動させる役割(演劇でいう道化)を担う探偵の山崎とサブ爺がいずれもサングラスをかけているのは偶然ではありません。彼らは赤の他人であるがゆえに、かなえや堀の心の底に流れる感情に触れることができます。真実と呼ばれるものは、目に見えないものであり、視覚に頼っていては何も見えないことを目隠しの役割を持つサングラスに象徴させているのでしょう。
本作を象徴するセリフのひとつに、探偵の山崎がかなえに投げかけた決定的な問いかけがあります。
人をわかるってどういうことですか?
悟の生とは、この根源的な問い(呪い)を日常生活のあらゆるシーンで突きつけられる日常です。
この問いが相手に対してだけでなく、自らにも刃を向けていることを彼は明瞭に切実に認識しています。
彼だけが、問いを誰とも分かち合うことができず、しかも決して答えにたどり着かないことを根底的に了知しているのです。
そのような人間は、厭世感により溺死する人生を送ることでしか、生を引き伸ばすことができません。
探偵の山崎がお膳立てした、かなえと悟の面談の場面にそのことが凝縮されて描かれています。
まだどうして出て行ったのか聞いていないよ
わたしの所では何がダメになったの?
どういうウソでいられなくなったの?
・・・僕は嘘つきだからね
君のことが本当に好きで
だから一緒にいるのがつらくなった・・・っていうのでどう?
表層が深層であり、またその逆も成立してしまう世界の住人の「アイラブユー」は決して届きはしないのでしょう。
もちろん、彼自身にも。
物語のラスト近くに登場する、懐に猫を忍ばせたサブ爺の容貌はどこまでも印象的です。実用的にカイロがわりに懐に入れているためであると思われますが、胸元から腹のあたりに顔を出す猫の「顔」に注意を払うならば、この人物の洞察力が人知を超えたものに由来していることが如実に表現されていることがわかるはずです。
顔を見せる暗流
本作を象徴するシーンは次の2つの場面です。
- 近所の子供の誘拐騒ぎにショックを受け寝込んでしまったかなえから、堀は首を締めて殺してほしいと懇願される
- 探偵山崎のセッティングにより対面する夫婦。悟の皮肉によって「最後に思いっきりひっぱたいていい?」と尋ねたかなえに対して悟は「いいよ」と呟き、目を閉じ静かに身構える
堀は、幼なき日のかなえのとった行動については当然に知るよしもありません。
彼女に罪はないと頭で理解しながら、彼女を許せない自身の暗流を彼は一瞬垣間見ます(見せられます)。
しかしながら、彼女の首に手を掛けることなく、彼女の涙を拭ってあげるのです。
この一連のシーンにおいて、作者は堀の心の内に渦巻く葛藤を丁寧に拾い上げます。
良識や倫理がもしかすると決壊するかもしれないその「危うさ」こそがここでは描かれているのです。
堀に対して立ち去るとき(退職する時)は黙って出ていかないでとかなえが懇願するのは、夫に黙って出ていかれたことの反復を避けたい気持ちからであろうことは容易に想像できます。と同時に、ある意味「黙っていなくなってしまったさなえ」を否応なく、より鮮明に思い出してしまうからなのでしょう。
一方、悟とかなえの話し合いの場においても、頬を打つと思いきや、優しい言葉をかけてかなえは彼の首にマフラーを巻きます。
これが純粋な思いやり(愛情・未練)からの行為であることの確証を得られないのは彼ばかりでなく、かなえ自身も同じであるはずです。
ここで頬を引っ叩く行為を選択しないことが、自分たちの別離を必然にしていることを二人は自覚しているに違いありません。
あたしたち もっと前に こんなふうに話せたらよかったのにね
うん・・・・
話せていてもいなくても、別れは不可避であったと、このやり取りは反語的に雄弁に物語っています。
ページを開くたびに新しい意味が生成する傑作です。
 パドー
パドー機会があれば、ぜひ手にとってみてください。
本作を男女のすれ違いという観点から見るのならば、女は最後までウソを突き通せと切望し、男は一緒にウソをつき合おうと懇願する図式となります。幸福には「真実」が全く無関係であり、かつ無用であることが図らずも明示されているのです。
 パドー
パドー愛の形は、男と女の数だけ在るか・・