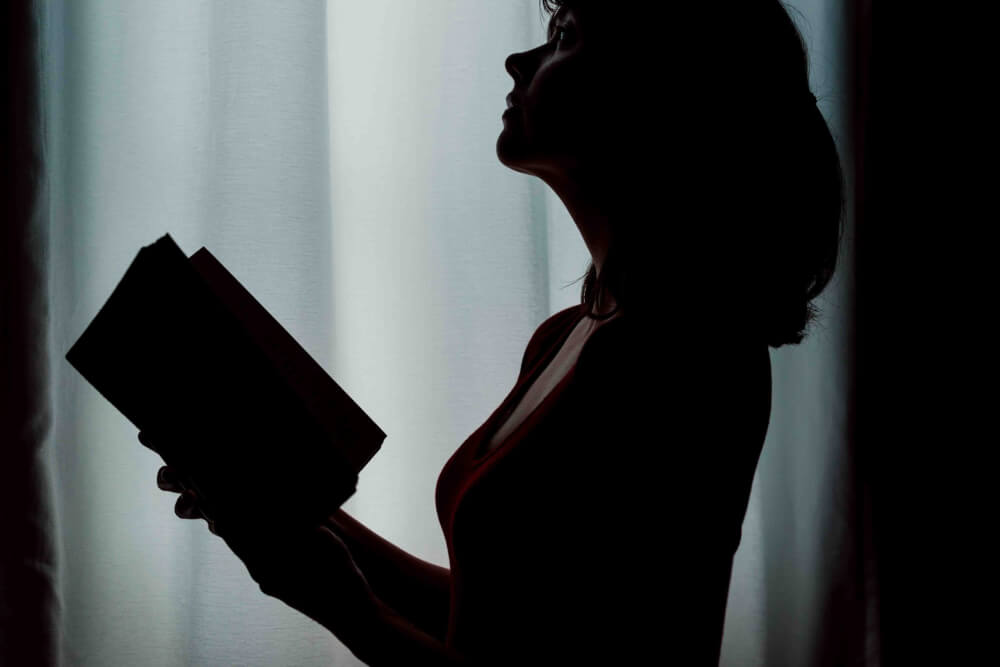今度こそ間違いなく、人の死なない漫画を描く
人気漫画「無限の住人」の作者である沙村広明氏が描く本作のコンセプトは「今度こそ間違いなく、人の死なない漫画」だそうです。
「人が死なない」とは、ある意味、日常の中の非日常性を中心に据えること、言い換えるのならば、非日常を前面に押し出す作品作りを放棄するという宣言に他なりません。
つまり、あなたの日常(生活)がそのまま舞台となります。
これは、物語構成・進行において、ドラマティックを極力排除しながら、日常のドラマ性をすくい上げる丁寧さが慎重に求められることを意味します。
内容の起伏さが乏しく、平々凡々になりがちとなってしまい、読者受けが難しい危険にさらされる可能性が高まります。
本作(シリーズ)はそのような杞憂をいとも簡単に吹き飛ばすほどのパワーに満ち溢れています。
以下、内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。
ストーリー
以下、掲載誌の「アフタヌーン」公式サイトからの引用となります。
鼓田ミナレ、独身女子、札幌在住。ひょんなことからギョーカイ人の中年男性にダマされ、ワケも分からずラジオDJデビュー!
鼓田(こだ)ミナレ、20代独身。札幌在住、スープカレー屋勤務。 ひょんなことからギョーカイ人の中年男性にダマされ、ワケも分からずラジオDJデビュー。カレー界とラジオ界の覇道を歩むべく奮闘はしないが、真の愛と幸せと享楽を求めてオンナは戦い続ける、に違いない。 さあさあさあ、波よ聞いてくれ!!!
私の場合、アニメ「波よ聞いてくれ」を視聴し、そこから原作のマンガに向かったファンのひとりです。
アニメの鼓田ミナレの圧倒的な存在感にKOされました。
作者あとがきから作品をみる
コミックス各巻の巻末に記される「あとがき」からは作者の生の声が聞こえてきて、作品理解にとても役立ちます。
本作は「ラジオと恋愛の話を描きましょう」という担当者の助言が出発点であったようです。
しかしながら、
2巻が刊行された時点においても、作者自身の「相変わらずのラジオと恋愛成分の少なさに驚愕しています」との通り、恋愛要素がほとんどなく進行します。
3巻に入り、「無軌道オカルトカレーラジオ漫画」との自己分析に至ります。
「あ?恋愛?知ったことではありませんね。」という開き直りのコメントがむしろ清々しいです。
4巻では、「夕暮れに飲んだくれ女達がクダをまくカレーとラジオの夢空間」と自作を定義づけます。
ここに至って、ようやく、それっぽい(恋愛マンガ)空気になってきます。
5巻では、「いつまでたっても雪が降らない北海道漫画」と、第三者からの指摘を受けての発言と見紛うコメントが出ます。
6巻では、「連載作品のほぼ全てに監禁シーンがある漫画家が描くラジオ漫画」という思い切った展開となった第6巻を象徴するコメントがなされます。
7巻では、作者自身の自虐的批評は控えられています。
本作より、北海道胆振東部地震をモデルとした地震被害の災害報道編へと突入していきます。
セリフがぎっしり
本作の特徴は、圧倒的なセリフ量です。
セリフの量が半端なくあります。
セリフ(特にミナレ)は、ボケやツッコミ、(自己)批評、諧謔に満ちあふれています。
溢れすぎて、ふき出し外の小さな書き文字がたびたび現れます。
ラジオの進行を意識させるような言葉の放射、シャワーに読者はめまいと同時に心地よさを体感するに違いありません。
いつまでもテメーが振り回せる女だと思ってんじゃねーぞ!!
「気まぐれ」がいついかなる時も許されるのはなァ・・・・
シェフだけなんだよ!!
波よ、私の思いを聞いてください
タイトルの「波よ聞いてくれ」はあらためて考えるとその意味を掴み取るのは簡単ではありません。
波(電波)、すなわちラジオ(番組)をできる限り多くのリスナーに聞いて欲しいという願いが、ラジオ番組制作者の目標であるはずです。
しかしながら、タイトルはその思いの方向が真逆です。
波に私(私の思い)を聞いて欲しいというのです。
 パドー
パドー「波」とはなんでしょうか。
波を電波、すなわちラジオと限定するのならば、それはリスナー(不特定多数)に私の思いをわかってほしい、双方向的に心を通わせ、いい番組を作り上げたいという思いになるでしょう。
もう少しばかり踏み込んで、ラジオをラジオ番組関係者と仮定するのならば、彼女を見出したチーフディレクターの麻藤兼嗣を指しているのかもしれません。
つまり彼との今後の恋愛関係が示唆されていると言えば、言い過ぎでしょうか。
これとは別に、
「波」をもっと広く捉えるのならば、はかないものや消え去るものに対しての問いかけとなります。
確たる対象は特定できないのですから、ある意味、問わず語りであり、自問自答です。
自分で自分の心の声に耳をすます行いとなります。
過剰なセリフは、そうであればあるほど、本心を隠しているのかもしれません。
ミナレを筆頭とする登場人物たちが、自分の心の奥底にうまくチューニングできるのかどうかに今後目が離せません。
傑作です。機会があればぜひ手にとってみて下さい。