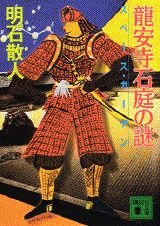コロンブスの卵が立つ
″目から鱗がとれる″と人が口にするとき、そこには新鮮な覚醒が鳴り響いています。
一方、
″コロンブスの卵″という格言には「なんだそんなことか」という素直に認めがたい感情が沈殿しているはず。
茹で卵を立ててみろと云われて、一生懸命にバランスをとろうとする度ごとにひっくり返してしまう人々をよそに、
コロンブスはその卵の底を少しばかり凹ませて見事にそれを立たせてしまうのです。
それを目にするやいなや、なんだそれじゃあ話が違うとか、卵に細工をするのはルール違反であると言い募り悔しがる凡庸な心は、自らの不自由さにはやはり目を瞑ったままでいるのでしょう。
驚きたがるこころ
本来、そこで鱗がハラハラと落ちるべきはずである人々の頭と目は異常な硬さを示すばかりです。
俺のウロコはそんな子供だましみたいな簡単な思いつきでは剥がれないんだとばかりに、逆に頭の硬直性ばかりを主張してしまいます。
たとえば、目に「卵」が付いているのなら、誰もがそれに気付き外そうとするはずです。
あるいは、
「鱗」を立たせろと謂われれば、天才と酔狂人だけが徒労を重ねることがあるかもしれません。
けれども、
そこには″普通の驚き″が抜け落ちているのです。
考えるための読書
人は、ほんの少しだけズレた位置から自分を取巻く世界がこんなにも変わって見えてしまうことに″wonder(驚き)″を見出せる生き物であると言えます。
短所の死角に長所が隠れてしまっているように、″wonder(喜び)″は些細なことの傍らにいつもじっと息を潜めています。
世の中には、ものの見方や発想法など、「考える」ことに関する書物が次から次に出版され、後を絶ちません。
けれども、それらは玉石混合であると言わざるをえません。
役に立つ本がたくさんある一方で、頭が良くなったと錯覚をもたらす本も少なくありません。
だがしかし、
明石散人氏の『龍安寺石庭の謎』はそれらの″実用書″とは根底的に異っているのです。
驚きの書
明石氏は凡百の書の如く、これをやれば、これさえ知っていれば、「コロンブス」になれるとも、なれとも決して言いません。
ハウツーやノウハウの提示はそこにはないのです。
ただ″総ての人間はある意味「コロンブス」である″と主張するだけです。
つまり、
自ら「鱗」を落とし続けようとする者だけが「コロンブス」であると云うばかりなのです。
「鱗」が落ちる落ちないはやがて微塵へと変わり果て、意味の彼方に消え入るでしょう。
落とし続けようとする試行(voyage)に、終り=目的(land)などありません。
明石散人=クリストファー・コロンブスは確言します。
″日常(everywhere)″こそが、″航海(wonder)″に他ならない、と。
もしかすると、
目と鱗が不可分である卵のような眼球の持ち主は、″石″に関するこの本を読めば、″固い″目玉ごと落っことしてしまうかもしれません。
だが、それもまた、ひとつの愕きでしょう。
否、切なる悦びなのです。