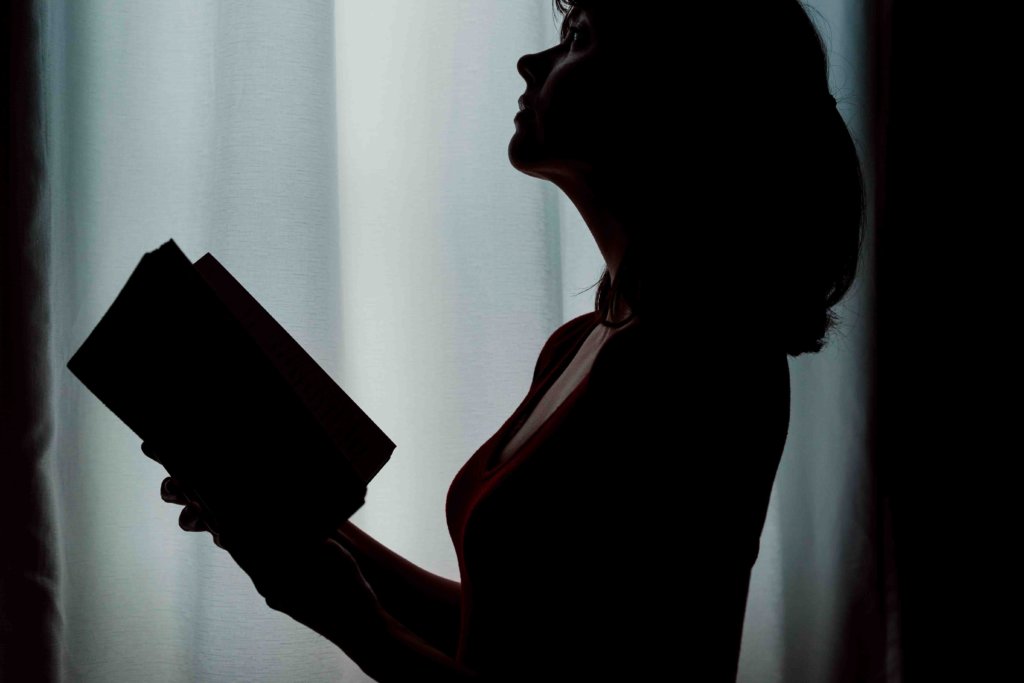ポール・ド・マン再会
本棚を整理していて、大昔に友人から頂いた書物が目に飛び込んできました。
 パドー
パドー懐かしい
当時は頑張って読んだ気がします。
まるっきりの空回りであったのですが。
分かるということ
かつて、柄谷行人氏は精神的師と言い得るポール・ド・マンの思想のエッセンスについて次のように述べています。
われわれはものが分かったと思う瞬間、″穴″に陥ってしまう。別の言い方をすれば、分かるということは、暗闇の中での″跳躍″に他ならない。
ド・マンの思想に触れるとき、我々は注意深くなければなりません。
ここで言われていることは、一読するだけでは論理的座礁を呈しているようにみえなくもないでしょう。
けれども、
真摯にこの一節に向き合うならば、彼が何を伝えようとしたのか、同じことだが、″何を伝えられないか″を″伝心″しようとしたのかが理解できるはずです。
穴に落っこちる
ご承知の通り、「ものが分かる」という経験はありふれています。
あなたにとってもそれは自明の事柄に属していることでしょう。
しかしながら、
そのような瞭然性にのみド・マンの視線は注ぎ込まれるのです。
それは「ものを早計に分かったつもりになることへの戒め」といった「自明」性に対する凝視とは無縁です。
そのような意味にとれば、別の″陥穽″に落ちるだけでしょう。
選択と放棄
「分かる」とは、″たったひとつのもの″を選び取る行為を指します。
すなわちそれ以外の可能性の純然たる「放棄」となるのです。
この必然を人は免れうることができません。
というのも、我々はその「選択」を選び終えることでしか物事が「了解」できないからです。
その選び取る行為には如何なる根拠も些かの理由もありはしないのでしょう。
認めたくはありませんが、ただ、根拠や理由があるようにみえる(思いたがる)だけなのです。
それは、あまりに巧妙に事後的に見出されてしまいます、どんなときも。
ある困難
たとえば、「分った」地点から遡行するとしましょう。
最後の最後に根拠や理由に突き当たるはずだというその″論理性″こそが人が落ち入る″穴″に違いありません。
しばしば、ありもしない事由や拠り所が「蔽い」となり「塞がってしまっている」場合が少なくないないのです。
きっと、論理的であることは「ものが分かる」ということと微塵の関係もないのです。
「ものが分かる」とは、″切断された不連続″な行いに他なりません。
幾ら″連続的″に理解を推し進めようとも、ひとは「分かる」という処に行けはしないのです。
決して予想もできず、見通すことも不可能である絶対的な″困難さ″が、「ものが分かる」という行為には常に付きまとわざるをえません。
と、ド・マンは云い続けているのです。
光明の瞬間
「わかる」とは文字通り「奇跡の到来」とでも呼ぶしかないものでしょう。
既知が連続する平原を直進するような気軽さからは、あなたは何も「知る」ことができません。
そうではなく、
一筋の光りもなき暗闇のなかの、一歩先が断崖である可能性が横たわる只中を飛び出さねばならぬ。
そのような瞬間に始めて「ものが分かる」という行為が開かれうるのです。
従って、
「ものが分かる」とは、″唐突″であり″野蛮″なる一行為であると言い切れるのです。
優しい声で
何か行き詰まったような感覚が私を無条件に支配するとき、ド・マンのことばが語り掛けてきます。
「お前さんはものを分かっているのか」と謂われているような気持ちになるのです。
 パドー
パドー今もってわかっていません。スイマセン