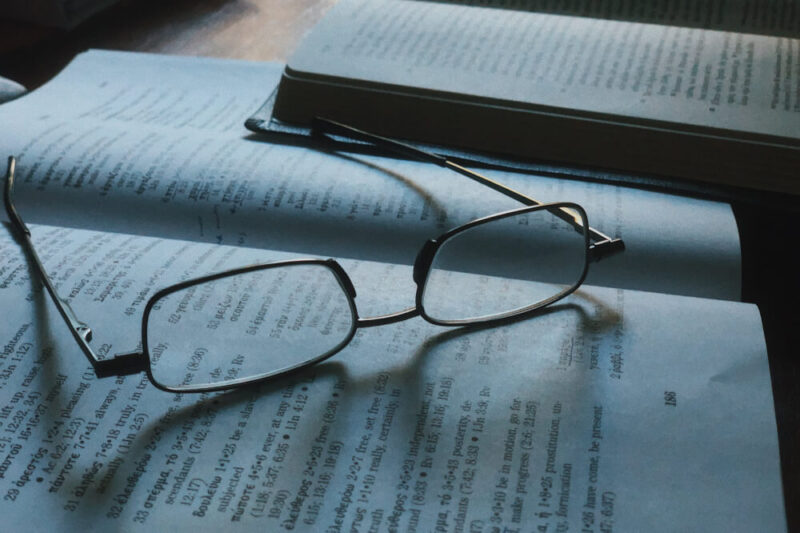行きたい大学に行くための勉強法を調べていたら、「参考書中心主義」という考え方に出会いました。なんだか光が差し込んできたよ、の一冊なのです
次男が今春希望の高校に入学しました。
現在は学校生活に少しは慣れたようですが、授業についていくのが精一杯のようです。
勉強の仕方がイマイチ不安である様子がうかがえます。
勉強法のヒントになるような情報はないだろうかと、少しばかり過保護が出てしまいました。
 パドー
パドーアマゾンで本書に出会いました。
まずは自分で読んでみて、これはなかなかいんじゃないかと思い、一度読んでみるように一週間前に勧めたのです。
読み進めている最中のようですが、悪くないという男子特有の褒め言葉が聞こえてきました。
見切り発車的ではありますが、急ぎ、ご紹介いたします。
今の時点で、実際的には成果は出ていません。
本嫌いの人間が、とにもかくにもページをめくり続けているという事実を重視しました。
2019年8月20日追記
2019年の春に改訂版が出版されました。
内容が大きく変わるところはありませんが、推薦する参考書が多少違ってきています。
2021年6月19日追記
マンガ版が出版されています。
こちらの方がサクサク読めます。
どんなひとが書いているのか
著者は独学で東大に入学後、大学院中退。
その後企業に就職し、現在は独立。
予備校を運営されているかたらわ、執筆にもお忙しいプロフィールの持ち主です。
本書のスタイル
ストーリー形式でとっつきやすいです。
勉強に不安を抱く高校生・田中真草くんが主人公となります。
趣味の古本探しで偶然訪れた「三陽堂古書店」との運命的出会いから、受験への考え方が一変する仕掛けのようです。
本当に効率の良い勉強法がストーリーで楽しくわかる新感覚参考書!
本書の内容を一言で言うと
参考書中心主義者になれ!
これは、参考書だけを使って勉強する人のことではありません。
参考書を軸に学習計画を組み立てる人のことを指します。
参考書至上主義ではなく、参考書中心主義なのです。
参考書中心主義ってなに?
参考書中心主義とは、参考書を最大限に利用し、自学学習を徹底的に行う考え方です。
自分で問題を解かないと力はつきません。
自分で問題を解く時間をできるだけ多く作るために、
すなわち、解ける力を養うために、参考書を縦横無尽に利用しろと主張します。
間違ってならないのは、著者は塾や予備校を否定していない点にあります。
自分で勉強することを軸にして、必要である講義であれば、塾や予備校の講義を利用するというスタンスで臨みましょうと述べています。
この考え方をできるだけ早く、多くの高校生に理解してほしいと思います。
 パドー
パドー特に塾や予備校に通っているだけでなんとかなるという幻想に蝕まれている人たちに。
塾や予備校に受け身で通っていても、決して実力はつかないのです。
参考書の紹介が素晴らしく、そのためだけに本書を買い求める価値がある
タイトルの通り、参考書の紹介がメインとなります。
紹介の仕方に一工夫が見られますのです。
目的別に参考書を3パターンで紹介しています。
- 理解を促進する参考書で下地を作る
- 網羅的な参考書で知識を体系化する
- ちょいずらし参考書で応用力をつける
複数の参考書が必要なためにある程度の出費は覚悟してください。
たとえば、
おいしいものを作るのに、目的別にいろんな包丁を持ちますよね。
包丁一本でなんでも捌けますは、名人だけでしょう。
我々凡人は、道具を揃えたほうが効率的で無難なのです。
ちなみに、例として世界史についてご紹介します。
理解の促進のために「ナビゲーター世界史Bシリーズ 山川出版社」
知識を体系化するために「世界史問題集完全版 東進ブックス」
応用力をつけるために「世界史B標準問題精講 旺文社」
参考書の編集者が考えていることも参考にしながらおすすめ本が選定されています。
 パドー
パドーそこのところは本書のユニークネスですね。
もちろん全教科紹介されていますので、詳しくは本書を手にとってご自身でご確認ください。
各章のまとめである「勉強の鉄則」が秀逸
各章のまとめとして「勉強の鉄則」が記載されています。
いわゆる本文のまとめ、エッセンスとなります。
時間のない方はここを読むだけでも十分に得るものは大です。
以下に、各「勉強の鉄則」の小見出しをピックアップします。
興味のある方はぜひ原本を手にとってじっくりとながめてみてください。
勉強の鉄則1
- 長く記憶するために、有意味暗記をする
- 自己流で解かない
- まずは自分が勉強できるようになる
勉強の鉄則2
- 目的を明確にした上で教育サービスを利用する
勉強の鉄則3
- 地方の公立進学校には自学自習をするための仕組みがある
- 成績がよくないのに塾に通うのは逆効果
勉強の鉄則4
- 都内の私立中高一貫校は受験予備校ではない
- 自分にとって理想の環境は、自分で創り出す
勉強の鉄則5
- 受験は時間との勝負である
- 受け身で受講するのは、時間対学習効果が低い
勉強の鉄則6
- 成績=学習時間X学習効率
- 高校一年生から受験勉強を始める
- 学習時の工夫が学習効率を高める
- 架空のライバルを作ってモチベーションを維持する
勉強の鉄則7
- 数学は計算力がないと点数が伸びない
- 式展開の意図を読む
- わからない問題はすぐに解説を読む
- 過去問は時間を計って解く
勉強の鉄則8
- 「やればできる」という学習観を持つ
- 勉強は難しくて当たり前だと考える
- 入試では出題範囲と出題パターンが決まっている
勉強の鉄則9
- 暗記はトイレや机まわりの壁を活用する
- 英語は単語(熟語)と文法(イディオム)が重要である
- 長文読解では、英文を頭から訳していく
- 構文と型を覚えたら和文英訳も自由作文もできる
勉強の鉄則10
- 化学、物理はリアルに起きている現象をイメージできるようになろう
- 生物、地学は有意味暗記をするよう工夫する
- 教科書傍用問題集をやりこみ教科書をチェックリストとして利用する
- 基礎のない人が使うと毒になる問題集がある
勉強の鉄則11
- 因果関係を掴むこと、感情を伴った暗記をすることを心がける
- 一問一答系問題集と理解系参考書の往復が成績を伸ばす
- 早い段階でアウトプットをする
勉強の鉄則12
- 現代文では、肉付け部分を削り著者の主張を見つける
- ボキャブラリーが増えると読解しやすくなる
- 古文は単語と文法を、漢文は句型を覚えることが9割
- 「時間をかけすぎない」が国語のポイント
勉強の鉄則13
- 1冊の参考書を短時間で5周以上する
- 教科ごとの時間配分を間違えない
- 過去問演習で合格最低点との差分を知り、時間配分を最適化する
ツボを押さえています、本書は
数年前に長男の大学受験のために、受験に対する考え方や効率的な方法、予備校の講義、有効な参考書問題集をそれなりに調べ検討した過去を私は持ちます。
そのとき身につけた情報をもとに本書の記述を追っかけると、その内容は極めてオーソドックスで的を得たものであると納得できました。
はじめての一冊としては高校生にはうってつけの一冊であると結論付けます。
不安であるなら、まずは本書を手にとってみればいい
自分でが言うのも何だが、
僕は人より少しだけ読書が好きという以外はどこにでもいる普通の男子高校生だと思う
近所の公立中学を卒業した後、近くの公立高校に入学 /それからあっという間に一ヶ月が経とうとしている
こんな僕にも志望校があって、それは難関大学と言われる大学なのだけれど
本当に今のままで合格できるのか、一抹の不安を抱えている
そんなある日 /僕はふらりと神保町に立ち寄った
それが僕にとって大きな転機になるとはその時思ってもみなかった
とても魅力的な文章です。
イラスト付きの非常に印象的な導入部分となります。
あなたもごく自然に本書にすべりこんでいけるでしょう。
 パドー
パドーあなたが行きたい大学に行くためのあなたの勉強法がきっと見つかるはずです。