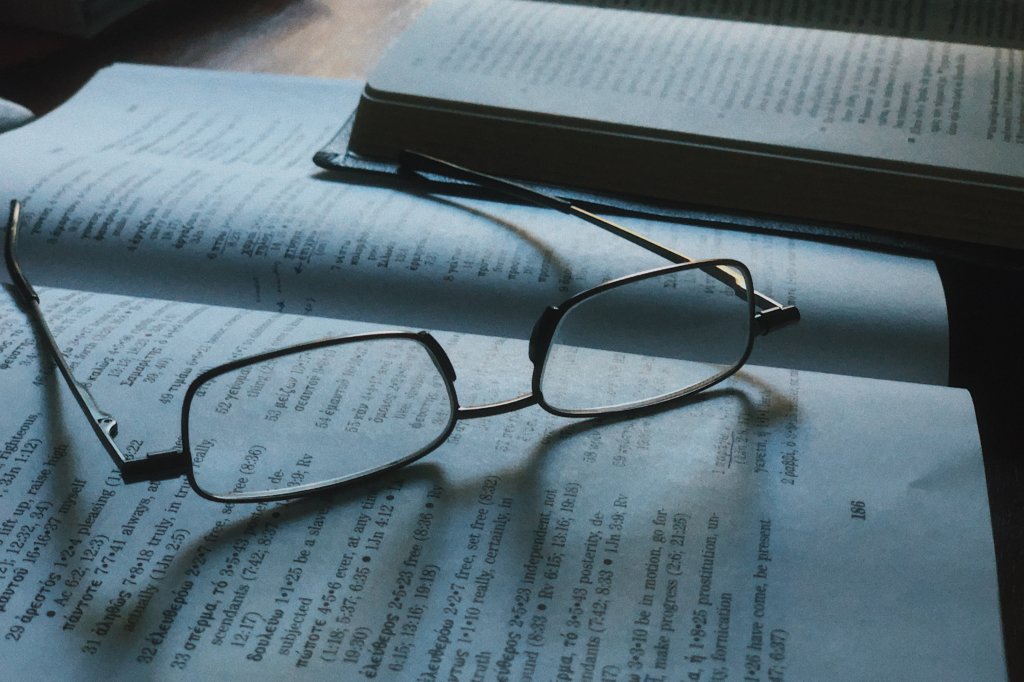世界を見る目を一変させる新たな「視点」を学ぼう!
現在シンガポールに在住し、東南アジア投資事業を展開されている著者の蛯原健氏は、本書のテーマである「テクノロジー思考」を次のように定義します。
近年において世界のあらゆる事象、組織、そして人間にテクノロジーが深く関与し、また支配的な存在として強い影響を与えている事実に焦点をあてた、新しい思考アプローチ
本書で目指されているのは、
テクノロジーそれ自体の正しい理解ではなく、
テクノロジーの在り方を正しく理解することにあります。
言い換えるならば、
テクノロジーの歴史やそこから演繹される未来、あるいはテクノロジーの人間社会に対する可能性や適用手法、インパクトを正しく理解することである。
本書はまさに私が普段実践しているテクノロジー思考をもって世界を眺めるプロセスそのものを記述し、1冊の本にまとめたものである。
ここであなたに質問です。
インターネット産業は成長産業でしょうか?
著者は断言します。
インターネットはもはや成長産業ではない。他の多くの産業と同じように成熟したレガシー産業である。
「成長産業である」と答えたあなたは、誤った現状認識の持ち主なので、本書を手に取りましょう。
「成長産業ではない」と答えたあなたは、現在の認識を維持拡大するために進んで本書を手に取るべきです。
 パドー
パドーこれからの時代において、普段の仕事や生活に役立つ実践的な思考様式をあなたは手に入れる必要があるのです。
本書の構成について
本書は、全部で10のパートから構成されています。
本書の構成
- テクノロジー思考とは
- テクノロジー産業の現在
- イノベーション至上主義と、スタートアップ全盛時代
- 次なるフロンティアはどこにあるか
- データ資本主義社会
- 欧州という現代のデータ十字軍VS.データ中央集権企業群
- インドー復権するテクノロジー大国
- 中国テクノロジーの正体
- 米中テクノロジー冷戦とは結局のところ何か
- テクノロジー思考の実践に向けて
- 本論となる第一章から第八章までは、産業・政治・国際関係分析などの今日的テーマについて、テクノロジー思考を用いて論じられています。
- 終章においては、テクノロジー思考それ自体を、すなわちテクノロジーと人間社会の接点を紐解く際の思考アプローチについてまとめられています。
テクノロジー思考の3つの特徴とは
テクノロジー思考には3つの特徴があります。
- 具体と抽象の行き来
- 組み合わせ
- 未来論
具体と抽象の行き来
- 具体とは、物質ないしは物理現象です。
- 抽象とは、概念に他なりません。
人間は基本的に具体と抽象によって成り立っています。
人間の生み出したテクノロジーにおいてもこの「具体」と「抽象」は本質的なものと言えます。
目的という抽象と、法則性と再現性を獲得した物質や物理現象という具体の融合こそがテクノロジーなのである。
著者は言います。
何らかのテクノロジーが現れたときに、
その具体(素材や物理現象)と抽象(目的の有無およびその高度さ)に注目することが大事であると。
つまり、
そのテクノロジーの発展段階や人間社会に対するインパクトを洞察するためには、具体と抽象を行き来しながらアプローチすることが決定的に重要なのです。
テクノロジーとはすべからく具体と抽象との間の行き来を繰り返す作業によって人類が勝ち取ってきた戦利品である。そしてこのような作業の連続性こそが人類の発展そのものなのである。
組み合わせ
テクノロジーとは複数の組み合わせによって初めて実用化し、かつそれはほとんどの場合、新規に誕生したから必要十分な成熟を経たテクノロジーによってなされるという特質を持っている。
しかしながら、それだけではありません。
テクノロジーは、産業や市場、あるいは顧客との組み合わせ、ないしはそれらが有している問題やニーズとの組み合わせがあって初めて社会に役立ち、したがって収益を生み出し得る問題解決策となる。
社会問題や顧客ニーズとの組み合わせによって、テクノロジーは初めて大きな価値を世の中に提供でき、社会的なインパクトを与えることができるのでしょう。
産業の革新とは常に次の2つのものの組み合わせであると著者は言います。
(1)ある技術と別の技術の組み合わせ。(2)技術と市場(ニーズ・問題)の組み合わせ。
未来論
未来に関する議論ほどテクノロジーが決定的に重要となるテーマはない。むしろテクノロジーを語ることは未来を語ることとニアリーイコールであって、逆も真である。
未来を見通すことの困難は誰も避けて通ることはできません。
けれども、あらためて考えてみてください。
あなたが生きる未来は自然にできあがったものではないのです。
未来はまぎれもなく誰かの手によって創られている。ことテクノロジーに関しては尚更である。
かつて、
「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」とアラン・ケイ(パーソナルコンピューターの父)は言いました。
発明は誰もが簡単にはできないが、それを「我が事」のようにとらえることはできるはずです。
「自らそれを創らない理由などない」という考えに基づき行動してきた者たちの努力の結晶がテクノロジーの歴史に他なりません。
テクノロジー思考を使って、あなたも「未来」にきっと加担することができるはずです。