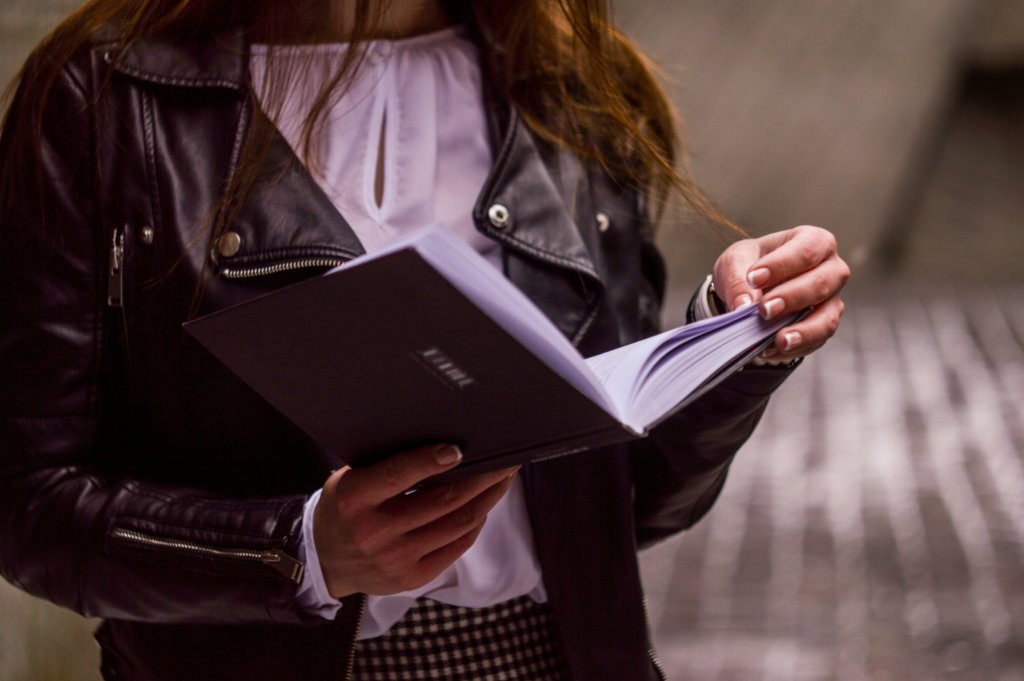1980年代の柄谷行人は向かうところ敵なしであった
現代日本を代表する思想家であり批評家でもある柄谷行人氏の名声を決定的にした本書は1985年に刊行されました。
「思考する機械」との異名を持つ柄谷の批評活動は、群像新人文学賞評論部門受賞作(1969年)である「<意識>と<自然>―漱石試論」からスタートします。
文芸評論家としての活動と並行し「マルクスその可能性の中心」を上梓したのち、やがて哲学的領域へ活動の軸をシフトしていきます。
本書「内省と遡行」は、盟友と言って差し支えない浅田彰氏が解説しているように「驚くべき戦争の記録」であり、「敗走」の書であると言えます。
しかしながら、「敗走」と呼ばれることはいささかも本書の価値を貶めるものではありません。むしろ、思考の徹底化が極限までなされていることへの最大限の賛辞に他ならないのです。
意識化の限界
本書は、ニーチェの問題意識を共有した上で、彼とは直接的な関係性が認められないフッサールの思想を丁寧に読み解きながら、多くの哲学者を参照しつつ、あくまで徹底的に思考の展開が図られます。
「哲学」は内省から始まります。
内省すなわち、意識に問うという行為は、本来的に、誰にも経験的であり明証的なものです。
したがって、我々はそこに疑義を生じる余地を見逃してしまいます。
意識に問う、言い換えれば、意識化するとき、我々は次のようなプロセスを意図的にであれ無意識にであれ、捉えそこねるでしょう。
ニーチェは言います。
私たちが意識するすべてのものは、徹頭徹尾、まず調整され、単純化され、図式化され、解釈されている
権力への意志
柄谷は次のように補足します。
意識に直接に問いたずねるということにおける現前性・明証性こそ、「哲学」の盲目性を不可避的にする。
これは別の言葉で言うと、我々は意識化(言語化・概念化)するとき、すなわち理解とは常に不完全である、と。
つまり、
哲学は、その始点である内省において、あらかじめ不首尾に至るがゆえに「敗北」が約束されてしまっていると言えるのです。
意識化することでしか、思考できない我々に、その限界をどうあっても超えることができないという結論が始終重くのしかかります。
柄谷の表現を借りれば、「内部に閉じ込められている」のです。
身体に問うとは
ニーチェは意識に直接問わない方法として、身体に問いたずねる方法論を提唱します。
我々が間違ってはならないのは、
それは意識を意識にとって外的な事実から説明するということではない
という柄谷の指摘です。
身体や生理学といった外的で客観的な事実は、意識の原因ではなく、結果に過ぎません。
すなわち、
すでに「意識」に絡めとられてしまっているからだ。
であるのならば、ニーチェの方法論はあらかじめ破綻しているのではないかという疑問が持ち上がるはずでしょう。
このような疑義に対して、柄谷は優れた次のような解釈を示します。
意識に直接問わないで身体に問うということは、意識に直接問いながら且つそのことの「危険」からたえまなく迂回しつづけるということにほかならない。
このような一連の行為(内省と遡行)が、精緻な繊細さを絶えず要求し、極めて困難な作業を要請することは容易に想像できるはずでしょう。
驚くべき戦争(敗走)の記録
意識について考えることは、意識化の限界をあらかじめ超えることができないがゆえに、追い求める「結論」に辿り着りつくことは決してありません。
内部にとじ込まれたままを意味します。
思考の袋小路で前にも後ろにも進めないのです。
ゆえに、
「結論」を求めるものは、結論(理由)を捏造します。
- 外部を何かポジティブに実体的に明示してしまう。
- あるいは、外部を詩的に語ってしまう。
柄谷は、そのような「安直」を自らに禁じ、徹底的に退けます。
内部に閉じ込められるのであれば、内部を徹底化し、自壊させるという戦術を選びます。
より根底的で徹底的な思考は「形式化の問題」へと至り、当然のように、形式度・抽象度の高い「言語・数・貨幣」の領域へと漂着します。
しかしながら、内部は自壊しません。
そのことを初めから、誰よりも解っていたのは柄谷本人であるはずです。
ゆえに、彼の思考の軌跡は「驚くべき戦争の記録(敗走の記録)」であると呼ばれなければならないのでしょう。
起源を問うことはできない
柄谷は、形式化の問題を考える過程において「自己言及性のパラドックス」に立ち向かうこととなります。
このパラドックスは簡略的に言うと、ひとつの体系内において正しさを証明する根拠を体系は決して持ちえないということを意味します。
つまり、体系の外に体系を担保する根拠が不可欠となるのです。
ゆえに、我々は、起源を問うことができません。
言い換えれば、意味の根拠に次々に遡行するのであれば、最後は「無」に突き当たってしまうほかないのでしょう。
「神」や「絶対」を持ち出し、見なかったことにする時代であれば、一応の決着はついていたはずです。
しかしながら、「神は死んだ」と宣言する哲学者にはそのような暫定的態度はとれるはずもありません。
ニーチェが内省についてどこまでもアクロバティックな態度を貫いたのは不可避でありました。
柄谷は本書の主要論考を書き上げる過程において、実際的な心身の危機、すなわち神経衰弱に陥ります。
30年近くも前に発表された本書が現在においても全く色あせることがない理由は、テーマの永遠性は言うに及ばず、著者がまさに命懸けで格闘した敗走(逃走)の記録であるからに他ならないからでしょう。