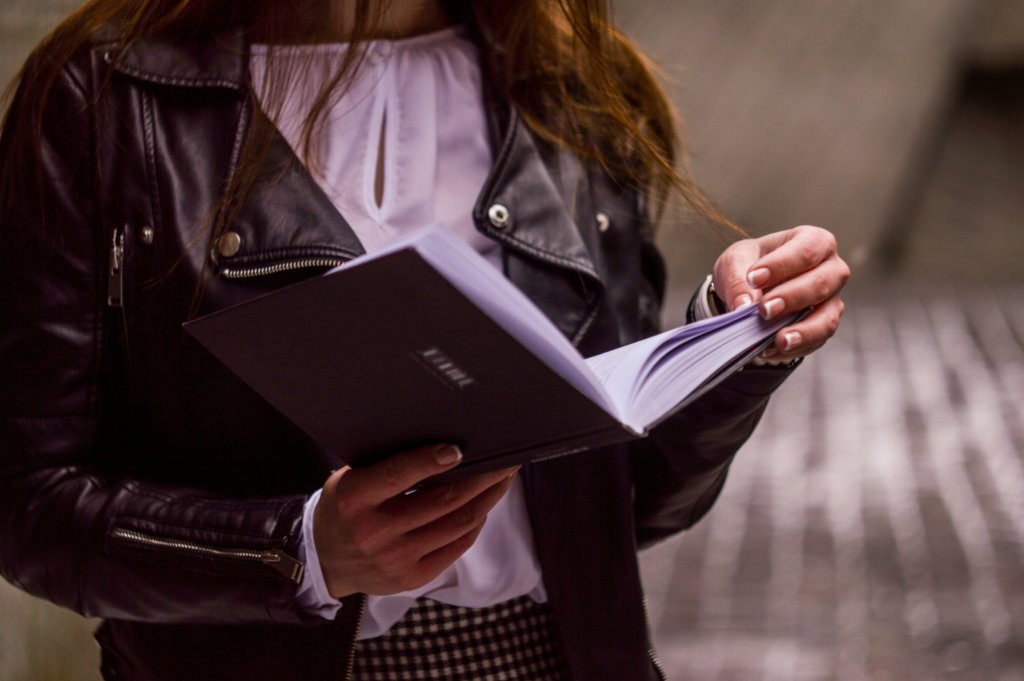鬼才川島雄三監督の渾身の一擲
1961年公開の本作「女は二度生まれる」は、川島雄三監督の大映での初監督作品であり、主演の若尾文子とはじめて組んだ傑作となります。
川島は、若尾を主演に据えて、本作を含め全部で3作品を撮っています。
- 「女は二度生まれる(1961)」
- 「雁の寺(1962)」
- 「しとやかな獣(1963)」
短期間のあいだに、日本映画史に残る傑作が続けざまに生み出されました。
川島が夭折していなければ、たくさんの名作・傑作が世の中にもっと残ったものと思われます。
以下に、本作を観て思いついたことを少しばかり記します。
内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。
川島作品におけるオープニングシーンのチャーミングさは、誰にも追随できない完成度の高さを毎度我々に見せてくれます。わずか数分程度の間に展開される情報量の多さと抜群の統制的構成はため息しか出ません。本作においても遺憾なくその才気が爆発しています。
あらすじ
戦災孤児だった九段の芸者である小えん(若尾文子)は、芸なしの不見転(みずてん)芸者(客の言うがままに身をまかす売春婦)であり、日夜不特定多数の男と関係を続けている。売春防止法により警察の手が及ぶと、商売替えをし、バーに勤め始めるが、そこで芸者時代の馴染み客の一人である一級建築士の筒井(山村聰)と再会し、彼の二号(妾)となる。小唄の稽古に励みながら、平安な日々が続くなか、筒井は突然に病魔に襲われ、入院中に帰らぬ人となってしまう。再び、花柳界に戻るものの、かつてのような一夜限りの「お供」を彼女は拒み続ける。かつての火遊び相手である若い職工の孝平(高見國一)と映画館のロビーで偶然出会い、そのまま二人で上高地に向かうが、孝平だけをバスに乗せ、自らは山に登らず終着駅に留まることを選ぶ。
100分足らずの上映時間にもかかわらず、映画的な時間の密度は尋常ではありません。
創意工夫に富むカメラアングルと抜群の編集テクニックにより、豊穣なる物語世界が実現されています。
なによりも主演の若尾文子の艶やかさ、可愛らしさ、美しさ、いじらしさ、凛々しさが、どの瞬間をとっても鮮やかに印象深くスクリーン上に留められているのです。
ショットの切り返し後の人物配置にこだわりが出ています。作為が過ぎる場面もなきにしもあらずですが、キャメラマンの意向が色濃く反映されたと思われる画面構成は、本作以降の作品においても継承されていきます。時々、息を呑むような「遠近法」も認められ、細部への神経の行き届き方が印象的です。
タイトルについて
公開当時のポスターの文句は次のようになっています。
はじめは女として
二度目は人間として
大映女性文芸大作!
容易に想像できるように、これはジャン=ジャック・ルソーの有名な文句を模して作られたフレーズです。
人は二度生まれる。
一度目は、存在する為に。
二度目は、生きる為に。
原作は富田常雄の「小えん日記」となりますが、上記のようなタイトルに変更したのにはもちろん理由があるはずです。
小えんが帯びている浮遊感や一種の軽さは、彼女の生き方や思想の現れというよりも、まるで現実から現実性が遊離している様が表現されているかのようです。商品化された身体にいささかの悲劇性も匂ってこないのは、このことと無縁ではないはずです。
タイトルの意味とは
タイトルの意味の解釈としては次のような解釈が一般的に成立すると考えられます。
女とは、もちろん主人公である小えんを指します。
戦災孤児として生きなければならない小えん(本名は磯部友子)は、生きるために芸者となり、春をひさぐ身です。
彼女は、毎夜違う男を相手にする自分自身の生き方に疑問を持ったことはありません。
しかしながら、筒井の二号となるうちに彼女の中で変化が起こります。
かつて淡い恋心が芽生えた、当時は学生であった牧(藤巻潤)と、ある夜の座敷で再会します。
会社勤めとなった牧は外国人客の「夜の相手」として小えんを指名するのです。
小えんは耳を疑い、何度も確かめますが、最後にそれを拒否します。
女の肉体を生活の道具とすることを拒絶するのです。
つまり、それは花柳界を去らなければならないことを意味します。
これもまた、偶然に映画館のロビーで再会した年若い弟のような存在であった孝平を誘い、彼が上高地のような山に行ってみたいとかつて口にしたことを思い出し、急遽二人で、長野県を目指します。
終着駅の島島(しましま)駅に到着するも、孝平だけを上高地行きのバスに乗せて、小えんはひとり駅に留まります。
ここで、男という存在と袂を分つことが端的に表現されています。
将来、彼女が自立して生きていくことが示唆されているのでしょう。
生まれ変わる予感がスクリーンを覆います。
これから先は、芸者としての「小えん」やバーでの通り名である「ともこ」ではなく、友子として(本名で)生きていくことが描かれているのです。
本作での山岡久乃の演技は「しとやかな獣」の出演時と比較して、ほとんど印象に残りません。むしろ、筒井の娘役の女優の演技が非常に印象的であり、不気味でした。
タイトルを深読みする
先に述べた一般的な解釈以外に、私は次の2つの意味をタイトルに見てしまいます。
 パドー
パドー極めて恣意的な見方となります。
タイトルにある「女」とは、日本国であり、女優若尾文子を指すと考えます。
「女」とは日本国である
当時の観客の多くは、本作が軍国主義批判であり、権威主義批判のフィルムであるとあまり意識していなかったそうです。
おそらく、
当時の社会にとって、あまりに当たり前の感覚すぎて、殊更に意識のうえに上ってこなかったからだと思われます。
今日的立場から本作を観た場合、余程の偏見がない限り、天皇制や軍国主義に対して、この映画は何かものを申したいのだろうと理解が及ぶはずです。
牧を戦後日本(日本政府)の矮小化された存在とする見方も、見ようによっては成立することでしょう。
節操なきご都合主義のリアリストとして。
しかしながら、
大国アメリカとの対比的存在としての位置付けを認めてしまうのであれば、手っ取り早く、女=小えん=日本国と見る方がある意味、見通しがいいはずです。
敗戦から、日本が立ち直ろう(二度生まれよう)としている姿が形を結ぶはずでしょう。
島島(しましま)駅から直ちに連想されるのは、極東の島国日本です。
ラストシーンにおける島島(しましま)駅にひとり座る小えんは、国家的自主を主張し、国際社会に独自の地位を確立しなければならない、頼りなげで不安定な日本国と二重写しになることでしょう。
事実として、上高地行きのバスが出ている鉄道の終着駅の駅名は島島(しましま)駅なのですから、ここには偶然的要素は何ひとつありません。
しかしながら、物語のラストの舞台をわざわざ長野県に移し、島島(しましま)駅を選択することは恣意的であり、演出的意図の賜物なのです。
小えんのクローズアップを排除し、固定されたロングショットによって、くすんだ色を基調とした風景の一部が切り取られている画があなたに示しているのは、敗戦から十数年経ったその当時も隠しても隠しきれない「傷跡」に違いありません。
その傷は、目に見える「外傷」であり、同時に内部に巣食う「欠損」であるのでしょう。
「傷」は国土の隅々に、民衆の心象風景のそこかしこに、残っています。
ロングショットが映し出すラストシーンは、荒涼とは言わないまでも、雑然とした気配に満ち溢れすぎているのです。
映画冒頭において小えんが身につけている市松模様の襦袢が紅白であったことは決して偶然ではありません。日章旗を容易に想像させる色彩配置が紛れもなく彼女こそが「日本国」であることを物語っているのです。
「女」とは女優若尾文子である
大映の看板女優のひとりであった若尾文子は、トップアイドルという世間的な位置付けに当時あったはずです。
30歳を前にして、いつまでも可愛らしさや初々しさで勝負する賞味期限は切れかかっていたに違いありません。
大映での初仕事である川島は、大映の幹部連中の前で、「この一作で若尾君を女にして見せます」、と啖呵をきります。
その覚悟は同等に若尾の中にもあったことでしょう。
色香、愛嬌、無垢、打算、狡猾、能天気、逡巡、清廉、決意。
次から次に万華鏡の煌めきの如く、多くのものを同時にいくつも求められたはずです。
本作を含め「妻は告白する(増村保造監督)」「婚期(吉村公三郎監督)」の三作品の演技が高く評価され、1961年のキネマ旬報賞とブルーリボン賞の主演女優賞の栄誉に輝きます。
これを機に若尾は、名実ともに正統派女優であり、演技派女優の王道を歩むこととなります。
女優若尾文子は、二度生まれた(生まれ変わる=脱皮する=化ける)と言えるのです。
ラストシーンが描出しているのは、女優の不安感や焦燥感ではもちろんなく、大女優が誕生しようとする不穏当さに他なりません。
映画の中で、筒井からプレゼントされた高級腕時計を孝平にくれてやる演出を思い出してください。
大女優の道程を進むべき者にとって、歴史(時間)は彼女の歩みの後ろにしか続かないものなのです。
若尾には、時計(決められた刻)は不必要であることが表現されていると言えば言い過ぎになるでしょうか。
彼女という存在は、フィルム的時間に選ばれたのです。
若尾文子の演技の凄みは、例えば、筒井が眠る墓参りのシーンに端的に現れています。墓石に水をかけ、柄杓に掬い取れない残り水を、桶を傾けて墓石に全てあけてしまうその一連の動作に、筒井に対する愛情と軽蔑と感謝と興醒めが凝縮されています。このような演技ができる女優はやはりどこを探してもいないのです。
何度でも観る
観れば観るほど、総合芸術としての映画の完成度の高さを思い知らされます。
映画にとって、現在のスタンダードである2時間は実に長ったらしい尺であることが理解できるはずです。
若尾文子という不世出の女優の魅力に溺死しても、もちろんいいでしょう。
映画的説話論法のマジカルに素直に舌を巻いてもいいはずです。
 パドー
パドー本作を通じて、日本が誇る天才(映画的才能)の成果物をあなたもぜひ堪能してください。