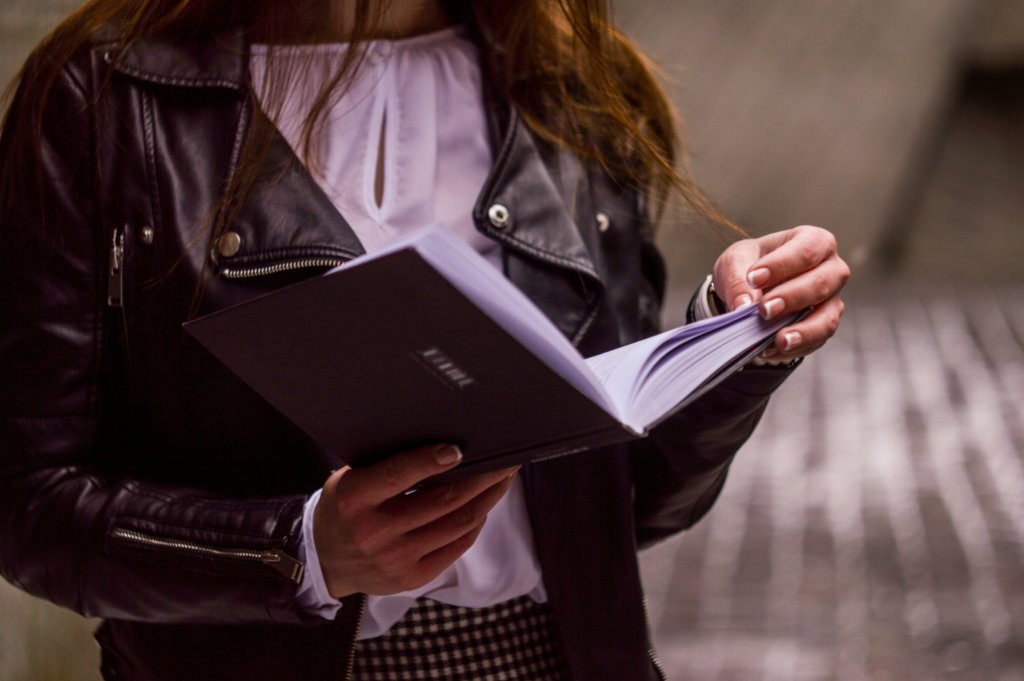世界のOZUは世紀の傑作になにを託し描こうとしたのか
小津安二郎の「東京物語」を久しぶりに観ました。
もう、何度目でしょうか。
悲しく、切ない映画です。
世界の多くの映画人が今もなお、絶賛し影響を受け続ける傑作中の傑作。
ここには、家族の普遍性と同時に「家族の一生」が紛れもなく描かれています。
今日は、語りつくされた感のあるこの名作について、以上の観点から少しだけ触れます。
内容に言及しますので、予めご了承ください。
あらすじ
1953年に公開された本作品のあらすじは以下の通りです。
尾道から上京した年老いた両親とその子供たちとの関わりが描かれています。
尾道に暮らす老夫婦は、東京に住む子供たちを久しぶりに訪ねるために上京します。
けれども、子供たちにはそれぞれ彼らなりの生活が確立されており、十分な対応をしてやることができません。生きるのに精一杯というのではないが、余裕が十分にはありません。
年老いた二人はある意味、子どもたちの日常にとって「違和」なのでしょう。
唯一の例外は、戦死した次男の嫁だけでした。
血の繋がらない彼女だけが熱心に二人の世話をし、親切を尽くします。
短い滞在の後、尾道に帰って直ぐに、老母が急死してしまいます。
葬儀のために子供たちは尾道に集まりますが、葬儀が終わるや否や生活のために、いそいそと逃げるように皆、尾道を後にします。
ここでも次男の嫁だけは、最後まで残り、例外的な対応を取ります。
彼女が帰ってしまうと、あとには飄々とした父親の一人きりの日常が続いていくばかりなのです。
全編を通じて、家族の絆、親子の関係、老いることと死ぬこと、人の一生が静かに抑えたタッチで描かれています。
見終わった後に、多くの人たちが親孝行をしなければと強く思います。
あるいは、
親孝行の機会を永遠に失った者は後悔の念に苛まれ、ある者は自らの境遇と重ね、むせび泣いてしまうかもしれません。
ここには時代を超え、国を超え、世界の誰もが思い当たるふしのある普遍的テーマが丁寧に取り扱われています。
皮肉を込めて、人を思いやる気持ちは血のつながりなどいささかも土台としていないことが逆説的に描かれています。
ここでは何が描かれているのでしょうか?
ここには、日本人の感性の露出ではなく、世界共通の家族のつながりと喪失という普遍性が焼き付けられています。
それゆえに、国を問わずこれほど大きな共感と賞賛を得ることができるのでしょう。
その意味で小津は「世界作家(映像作家)」です。
ここには明解に人生が凝縮した形で描かれていると言えるはずです。
それと同時に紛れもなく「家族の一生」が表出されています。
そう、「家族の一生」とはなんでしょうか?
家族の一生とは
赤の他人が一つ屋根の下に暮らすことから「家族」は始まります。
やがて子供が産まれ、子供は成長し、それぞれが家庭を持ち、あるいは家を出て行き、振り出しに戻るように二人きりになります。
これが家族の一生の代表的なサイクルです。
見誤ってはならないのは、小津は意識的に「戦後の核家族」に焦点を当てているという点です。
戦前の大家族では「二人きり」には決してなりません。
戦前の場合は「家族の一生」ではなく、「イエの一生」だけが忠実に繰り返されてしまいます。
このような点に小津が極めて同時代的な映像作家であったその資質がみてとれるでしょう。
我々にとって「在りし日」を感じさせる彼の作品の多くは、OZUにとっては「今日ただ今」だったのです。
もう、お分かりの通り、
家族の一生は幸せをスタートとし、子供の巣立ち、夫婦の死別という坂道を下る過程を経るサイクルをたどります。
異論もあるでしょうが、右肩上がりに幸福度が増す家族の一生というものはほぼありません。
そのピークは子供の誕生から中学校にあがるまでの期間であるといっても過言ではないのです。
子供の可愛い盛りと幸福度は正比例関係にあると言えます。
思い出してほしいのですが、この映画のなかで孫との触れ合いはきわめて限定的なのです。
家族の一生において孫は決して「メンバーでない」ことを明示するために制限がかけられています。
なぜなら、孫とは自分以外の別の家族(子供の家族)のメンバーであるからに他ならないからです。
長男との東京見物が急患のために急遽取りやめになります。孫は楽しみが台無しになり、上の子はふてくされます。気の毒に思った祖母の声がけとともに、下の子はとりあえず家の外に出ます。この土手の上での二人のシーンは本当に奇妙な光景を成立させています。本来であれば優しさや安寧が全面に出てきておかしくない場面であるにもかかわらず、画面の隅々に尋常でない強度が走っています。このようなフィルムの緊張度に孫と祖母との関係性が十分に現れていると感じざるを得ません。と同時に、後出しジャンケン的な解釈となりますが、祖母の周りにうっすらと死の影が漂い始めているというのは言い過ぎでしょうか。
腕時計の意味するもの
映画の中で、葬儀のあとに、年老いた父親は、妻の形見である腕時計を未亡人である次男の嫁に手渡します。
未亡人は感極まり号泣してしまいます。
この場面はみる者すべてに訴えかける名シーンです。
財産というほどの財産ではない形見の品はまさに老母を象徴する一品です。
それゆえに、彼女(嫁)に引き継がれなければならないことは了解できます。
われわれはそこに、義理の両親の優しさや思い出に突然強襲され、涙がとまらない未亡人の感情の激流を容易に認めることができるでしょう。
それと同時にわたしには次のような理由から未亡人が声をあげたのだと思わざるを得ないのです。
愛する夫の戦死によって、自らの家族の一生を永遠に奪われたその事実を腕時計の針の進みの中に決定的に見てしまったのだと。
現実には針は動き続けていますが、「義理の母親の人生が打ち止められたこと」と「自らの家族の一生は止まり続けたままであること」を二重写しに残酷にも思い知らされてしまったのです。
彼女が顔を覆って泣くシーンに続き、末の妹が勤務する学校の横の坂道を親子連れ(母親と二人の兄妹)が下る場面が続きます。ここに未亡人の「無念」を見てとることはそれほど難しいことでは決してないはずです。
この場面の後に、場面は教室で教える末の妹の姿に切り替わります。算数の授業であり、黒板に割り算の問題がいくつか書かれています。第一問が、92➗23、第二問が、72➗36となります。答えは、言うまでもなく、4と2。すなわち、「死に」が不吉にも明示されているのです。
家族にこだわる男
実生活において家族の一生と無縁であった男が、家族の一生の影の部分に光を当て、完璧なまでにフィルムに焼き付けたことは皮肉であるのか、必然であるのか。
その真相をもはや誰にも追っかけることはできません。
「映画という家族を持った男」は例外的に最後まで幸せな「家族」の一生の当事者であり続けたのは確かなようです。
 パドー
パドー見そびれるのならば、一生後悔するレベルの作品です。
まだご覧になられていないのであれば、ぜひ機会を作ってください。