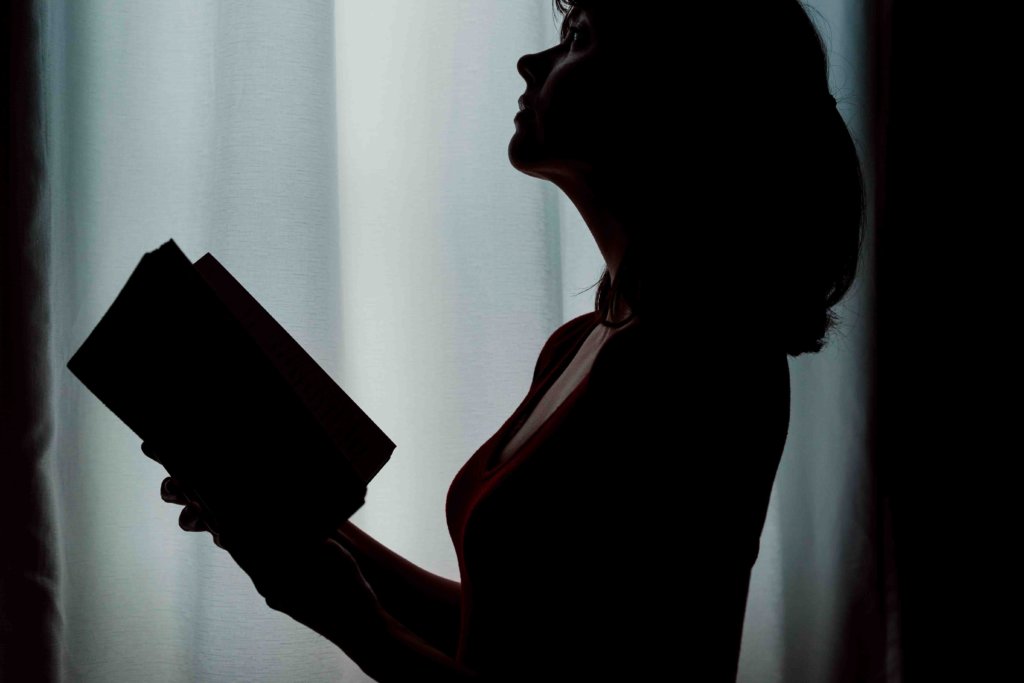村上春樹の大ベストセラー「ノルウェイの森」をまさか読んでいないとは言わせない
村上春樹氏の人気を不動のものにしたこの小説は1987年に出版され、出版から5年を経ずして累計1000万部を売りつくした大ベストセラー小説です。
彼のファンは言うに及ばず、普段「HARUKI」を読まない読者も一度は手にとったであろうと容易に想像ができます。
当時からクリスマスカラーである赤と緑のこの装丁は本当に目立っていました。
本日は、何度目かは忘れましたが、久しぶりに読み返したこの小説のテーマについて思うところを、以下に書き記します。
 パドー
パドー内容に言及しますので、あらかじめご了承ください。
100%の恋愛小説と呼ばれた物語のあらすじ
100%の恋愛小説と帯にあったと記憶します。
それまでの村上の小説とは一線を画し、軽妙なレトリックも極端に排除され、極めてリアリスティックに物語は構成され、進行します。
舞台設定は1960年代の終わりとなります。
主人公が神戸の出身であり、東京の私立大学で演劇を専攻していることや現在は書くことを仕事にしていることから、自伝小説の一種と捉える見方もありましたが、村上自身はそれを否定しています。
あらすじは、次のアマゾンでの紹介を引用します。
限りない喪失と再生を描く究極の恋愛小説!
暗く重たい雨雲をくぐり抜け、飛行機がハンブルク空港に着陸すると、天井のスピーカーから小さな音でビートルズの『ノルウェイの森』が流れ出した。僕は1969年、もうすぐ20歳になろうとする秋のできごとを思い出し、激しく混乱し、動揺していた。限りない喪失と再生を描き新境地を拓いた長編小説。
 パドー
パドー小説の冒頭部分がざっくりと切り出されているだけなので、いまいち伝わりづらいかな。
実は、この物語は2010年に映画化されています。
小説世界をできる限り壊さないように作られた良作です。
 パドー
パドーアマゾンビデオでの紹介文を引用しましょう。こちらのほうがより具体的でわかりやすいと思われます。
高校時代に親友・キズキを自殺で喪ったワタナベは、新生活を始めるために東京の大学に進学。そこで、偶然キズキの恋人だった直子と再会する。お互いに大切なものを喪った者として付き合いを深めていった二人は直子の二十歳の誕生日に一夜を共にする。しかし、ワタナベの想いが深まるほど直子の喪失感は大きくなっていく。そんな折、ワタナベは大学で小動物のように瑞々しい女の子・緑と出会う。
この物語は、死者あるいは死そのものに取り憑かれた人物により渋滞しています。
 パドー
パドー次に、その点について登場人物を紹介しながら触れていきます。
生きることに複雑骨折したひとびと
主要人物は8名となります。
- 主人公のワタナベトオル
- 直子(高校時代の親友の恋人。現在はワタナベの恋人のような存在。精神を病み、後に自殺する)
- キズキ(高校時代の親友、高校時代に自殺)
- 緑(大学の友人。恋人になる可能性がほのめかされている)
- レイコ(直子が入っていた療養所のルームメイト。精神を病んでいる)
- 永沢(ワタナベと同じ寮に住む東大生。外務省に入省予定)
- ハツミ(永沢の恋人。永沢と別れた後、別の男性と結婚するが後年自殺する)
- 突撃隊(寮でのワタナベのルームメイト。後に退学(休学)する)
死の影が色濃く反映した人物配置となっています。
あの頃(政治の季節)特有の息苦しい空気感が影響していることは否定できないでしょう。
このような極端な物語設定についてはもちろん明確な理由があります。
カジュアリティーズとは?
村上春樹自身は「ノルウェイの森」について次のように言及しています。
そしてこの話は基本的にカジュアリティーズ(うまい訳語を持たない。戦闘員の減損とでも言うのか)についての話なのだ。それは僕のまわりで死んでいった、あるいは失われていったすくなからざるカジュアリティーズについての話であり、あるいは僕自身の中で死んで失われていったすくなからざるカジュアリティーズについての話である。僕がここで本当に描きたかったのは恋愛の姿ではなく、むしろカジュアリティーズの姿であり、そのカジュアリティーズのあとに残って存続していかなければならない人々の、あるいは物事の姿である。成長というのはまさにそういうことなのだ。それは人々が孤独に戦い、傷つき、失われ、失い、そしてにもかかわらず生き延びていくことなのだ。
自らの著作の選集に寄せたこのコメントは非常に興味深いです。
コメントからこの小説の狙いが明瞭に理解できます。
「損なわれた者それ自体の姿」と「生き延びることの懸命さ」を恋愛という過程を通じてあぶり出そうとした小説であると言えるのです。
この視点から先の8名をあらためてみると、見事に死屍累々の山としか言いようがありません。
主人公と永沢以外のレイコ、緑、突撃隊は死亡確認はされていませんが、ある種の行方不明状態にあると言い得ます。
我々の生のうちに潜んでいるものの正体
なぜこれほどまでに、生きることの困難さが執拗に描かれるのでしょうか。
そのことについて、村上は処女作以来たびたび小説内で言及してきました。
「ノルウェイの森」においても、通低音のように旋律は響いています。
キズキが死んだとき、僕はその死からひとつのことを学んだ。そしてそれを諦念として身につけた。あるいは身につけたように思った。それはこういうことだったのだ。
「死は生の対極にあるのではなく、我々の生のうちに潜んでいるのだ」
たしかにそれは真実であった。我々は生きることによって同時に死を育んでいるのだ。しかしそれは我々が学ばねばならない真理の一部でしかなかった。
村上春樹も本質的な作家の例に漏れず、「死」と真正面から取り組んでいる職業作家のひとりです。
死の描き方は作家の数だけありますが、彼の認識は首尾一貫しています。
死は生の対極にあるのではなく、我々の生のうちに潜んでいるのだ
死が生の対極にあるのならば、おそらく、弾けるような眩しさの恋愛小説が展開されていたことでしょう。
しかしながら、そのような「明るさ」を書くことはできません。
彼が不本意ながらも100%の恋愛小説という宣伝文句を了承したのは、必ずしも商業的立場をわきまえたからだけではなさそうです。
「損なわれた者それ自体の姿」と「生き延びることの懸命さ」は恋愛というフィルターで濾過されることにより、凝縮され、結晶化することを知り抜いていたからに違いありません。
ゆえに「恋愛が主役の小説」でなければならなかったのです。
大作家が生涯にわたって追い求める「文学の大票田」である「死」と「恋愛」が、高次でクロスした物語が生まれたとき、多くの読者に称賛をもって迎えられることは自ずから約束されていたのでしょう。
 パドー
パドーすでに読んだことのある方も、もう一度、心地よい読書の時間を持ちませんか?