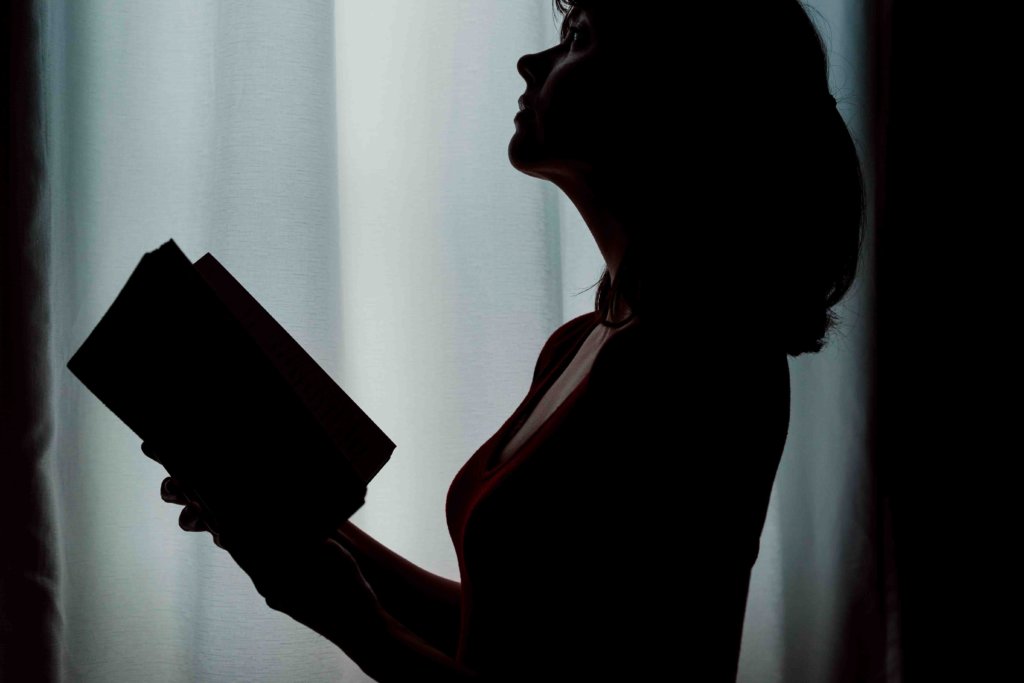映画「光」に描かれる光とは何を意味するのだろうか
2017年に上映された河瀨直美監督作品である本作は、第70回カンヌ国際映画祭でエキュメニカル審査員賞を受賞しました。
 パドー
パドーカンヌにご縁のある監督です。
本作は、弱視の男性写真家、中森雅哉と視覚障害者用のために映画の音声ガイドを製作する女性、尾崎美佐子の人生の交差を描いた作品です。
公式サイトには次のようにストーリーが要約されています。
単調な日々を送っていた美佐子(水崎綾女)は、とある仕事をきっかけに、弱視の天才カメラマン・雅哉(永瀬正敏)と出逢う。美佐子は雅哉の無愛想な態度に苛立ちながらも、彼が過去に撮影した夕日の写真に心を突き動かされ、いつかこの場所に連れて行って欲しいと願うようになる。命よりも大事なカメラを前にしながら、次第に視力を奪われてゆく雅哉。彼の葛藤を見つめるうちに、美佐子の中の何かが変わりはじめるー。
以下、内容に言及しますのであらかじめご了承ください。
向いていない女
映画の音声ガイドのナレーションを作り上げる場合、視覚障害者をモニターとして招き、彼らの意見を反映しながら、制作が進められます。
映画の音声ガイドとは、登場人物の動作や情景を言葉で伝える仕事となります。短い時間の中で的確な表現が求められ、高度な技量が問われる仕事です。
その過程において、ある劇中映画のナレーションのベース作りを担当する美佐子と遠慮を知らない雅哉の間で、解釈の違いや意見のぶつかりあいが生じます。
他の視覚障害者からも、遠回しに美佐子のナレーションに対する不満が口にされるほどに彼女の表現は推敲の余地が大ありの出来です。
偶然から雅哉の自宅を訪ねることになる美佐子は、そこで「この仕事に向いていない」とはっきりと言い渡される始末です。
劇中映画の監督にインタビューする機会を得て、映画のラストシーンにおける自分の解釈についての意見を監督に求めますが、何もわかっていないという感じで、インタビューは時間切れ終了となります。
映画の前半において、美佐子は、他人に対する想像力の欠如した人間であることが徹底的に描かれます。
折り合いがつけれない男
名のしれた元写真家の雅哉は、今は生きるために自宅でできる違う仕事についており、その合間にカメラを片手に外に出る生活を続けています。
彼は、徐々に進行していく失明の恐怖と戦いながら、自分に降りかかる運命を受け入れることができません。
頑なに、杖を使用することを拒み、周りに対して攻撃的な態度を決して抑えようとはしないのです。
映画の前半において、雅哉は、他人に対する想像力の欠如した人間であることが徹底的に描かれます。
解釈の食い違い
劇中映画のラストシーンにどのようなナレーションをつけるのか。
ここが、本作の白眉となります。
砂丘を登っていく老人(劇中映画の監督自身が主人公を演じています)の後ろ姿。
その先には太陽の光が見てとれるラストシーンに対する美佐子の最初のナレーションは「希望に満ちた表情」という過剰な説明がなされます。
しかしながら、
彼女には彼女の言い分が存在します。
子供の頃、父親が失踪し、父親との思い出が山の上で二人で見た夕陽であるという過去を持つからです。
美佐子にとって、光とは希望の象徴のようなものに他なりません。
一方、
光をどう表現するかという仕事を生業としていた元写真家にとって、
瞳から光が奪われようとしている現在の境遇において、光そのものを一義的に理解することは不可能です。
人生そのものであった「光」に対する強烈な思いは捨てきれません。
光が奪われることからくる絶望に抗い、精神を正常に保つためには、光を憎むべき対象へと変換しなければならないという諦念が無残にも彼を引き裂きます。
ゆえに、
彼にとっては彼女の楽観に過ぎることば(解釈)は断じて受け入れることのできないものなのでしょう。
ナレーションをブラッシュアップする過程において、美佐子は悩んだすえに、言葉を省略する安直な策に流れます。
雅哉はそのような判断を「逃げ」であると辛辣な言葉を浴びせるのです。
ラストシーンのナレーション作りは当然のように暗礁に乗り上げます。
光とは何か
本作のラストは、劇中映画の完成披露上映となります。
このナレーションの声は樹木希林となります。言葉がしみ込んできます。
焦点となったラストシーンには次のようなナレーションが施されます。
重三の見つめる先。そこに光
光とは何か?
それは「希望」を指すのでしょうか。
それほど単純な話ではなさそうです。
端的にいうと、
「他者に対する想像力」を意味します。
別の言葉で言い換えると、
「待つこと」となります。
待つこと
「待つこと」は、本作のラスト近く、親密な関係となった美佐子と雅哉のやりとりに象徴的に描かれています。
彼女のアパート(もしくは彼のアパート)へ杖をつきながら雅哉がゆっくりとひとり歩いてきます。
ベランダから彼の姿を認めた美佐子が言います。
中森さん。そっちに行きます。
彼はそれをしっかりと拒絶します。
待って。俺は追っかけなくても、探さなくても大丈夫だから。ちゃんと、ちゃんとそこに行くから。だからそこで待ってて。
ここでは、失踪した父親に絡めとられる人生をもう終わりにすべきだとの美佐子へのメッセージが放たれています。
過去を追い続けることはもう終わりにしなさい、と。
と同時に、
これまでの人生を脱ぎ捨てる(捨て去る)ことのできる自分に出会うまで、焦らず腐らず絶望せずに「待つこと」を彼は自分自身に言い聞かせているかのようです。
受け入れる自分を自らが「待つ」のです。
思い出して下さい。
表現者である劇中映画の監督は、最後のシーンに対する解釈を美佐子に押し付けはしませんでした。
この行為は「他者に対する想像力」の発露であり、「待つこと」の典型的な実践であると言えます。
理解を振りかざし、勝手に相手の方へ「走って」行かない。
性急に答えを求めずに、出さずに「待つ」。
時を待ち、他者を待ち、自分を待つ。
光は沈黙しながら、全てを語っています。
誰かのせいにしたくなる日々が続いている時は、ぜひこの映画をご覧になってください。
少しばかり、他人にも自分にもきっと優しくなれるはずです。