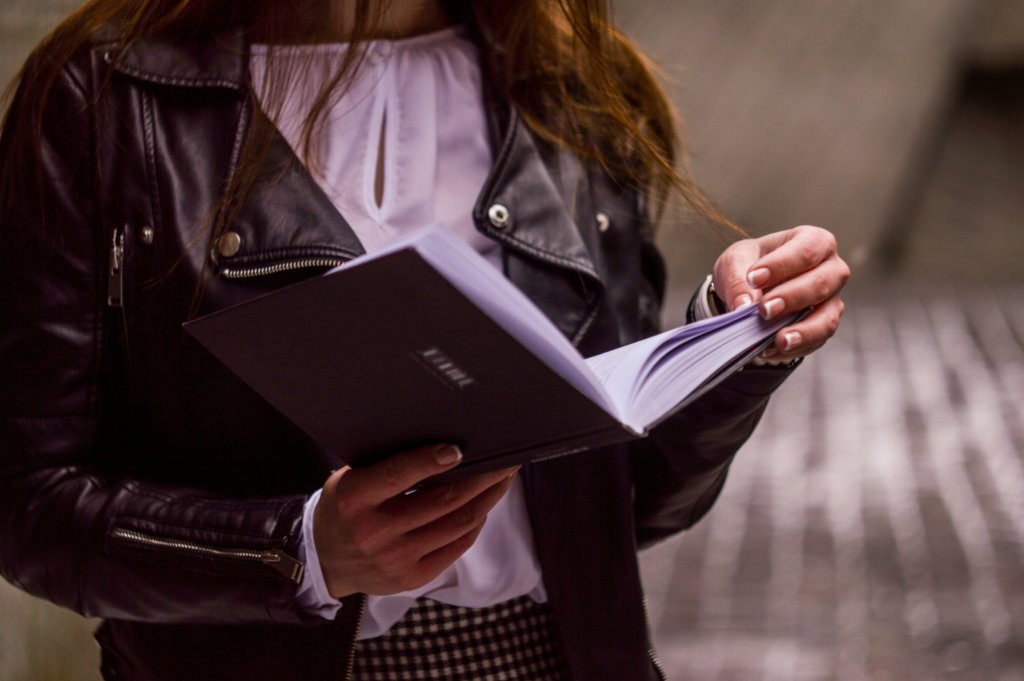生活の基本的要件としての「住」の位置づけ
屋根のない「むき出しの場所」で生き続けることは極めて困難です。
自然でろうが人工であろうが、直射日光や雨風を防ぐための、屋根や外壁が必要となります。
雨天も炎天も生命を脅かします。
そのために、頭の上に傘(笠)が必要となるのです。
自然の直撃からどう身を守るのかが生き物である限り、誰にとっても死活問題であるはずです。
外部からの遮断。それが住居の主要な役割です
傘(笠)を見つけたり、作ったりして、それで終わりではありません。
その次に、人は外部と内部を分けることを欲します。
内と外に分けることによって、空間は「公的なもの」と「私的なもの」に区切られます。
 パドー
パドーなぜ、分けるのでしょうか。
快適さを確保するためです。
体の芯まで冷える雨粒や猛烈な日差しから逃れるために「傘」を求めました。
これは不快からの逃走です。
これとは異なり、壁をつくるとは快の追求がメインとなります。
- 冷たい風をしのぐ
- 外の寒さを和らげる
- うるさい音から遠ざかる
- 嫌な匂いを避ける
- 害虫から身を守る
- プライバシーを見えなくする
内と外の線引を徹底し、侵入を防ぐことが目指されたのです。
外部を導入しようとしてきた「住」
自然を遮断することを目指して始まった「住」の運動は、皮肉にもその内側に自然を導入し始めてしまいます。
 パドー
パドーある種の矛盾です。
現代においても、いくつもの例が散見されます。
- ウッドの多用(木の温もり)
- 採光の工夫(明るい部屋)
- グリーンの増殖(緑による癒し)
自然の猛威を避けながら、手のひらサイズの自然をこよなく愛しようとします。
経済的成功の象徴としての「住」を考える
本来、自然の厳しさから逃れるために必要とした屋根や壁、すなわち住まいは時代が進むにつれ、本来の目的から大きく逸脱していきます。
もしかすると逸脱ではなく、ある意味必然であったのかもしれません。
いわゆる「自分の家」志向です。
人は「自分の城」を持つことを夢見ます。
一国一城の主(あるじ)化が促進されました。
その中には時として本物の城へと向かう者も現れる始末です。
- 権力の象徴として
- 財力の象徴として
- 虚栄心のために
- 名を残すために
もっと高く、もっと豪奢に。
特異な位置を占める「住」
住は、お金をかけようと思えばキリがない類いのものです。
衣と同様に社会的地位や身分を直ちに知らしめる役割を担っています。
それでも衣食住と3つ並べたときに、その特異性は際立ってしまいます。
「住」の主(あるじ)はあくまでそこに住む人であるはずです。
けれども、いつのまにか「住」自体が主になってしまう。
衣食住のなかで、最も自分自身が主役になれないジャンルなのかもしれません。