2つの知性の交叉
日本が誇る知の巨人と言えば、その筆頭にあげられるのが南方熊楠(みなかたくまぐす)であるとする主張に異を唱える者はほぼいないでしょう。
彼は明治時代の後半に、同じく真言宗の名僧として著名な土宣法竜(ときほうりゅう)と夥しい数の手紙のやりとりを残しています。
ふたりの間に交わされた往復書簡の文面に、われわれがよく知る「因果」についての説明があります。
その因果とからめて、われわれにはあまり馴染みのない「縁起」のことについても触れています。
短い記述であるにもかかわらず、その考察は非常に深く、示唆的であると言えます。
以下に、熊楠の手紙に記されている因果と縁起に関する彼独自の説明(分析)について触れます。
 パドー
パドー引用元は、河出文庫「南方熊楠コレクション」の南方マンダラからとなります。
因果について

明治36年8月の法竜宛の手紙の中で、熊楠は次のように書いています。
因はそれなくては果はおこらず。
物事(現象)にはその原因が必ず存在します。
また因異なればそれに伴って果も異なるもの、
原因が違えば結果も当然に違ったものとなります。
縁起について
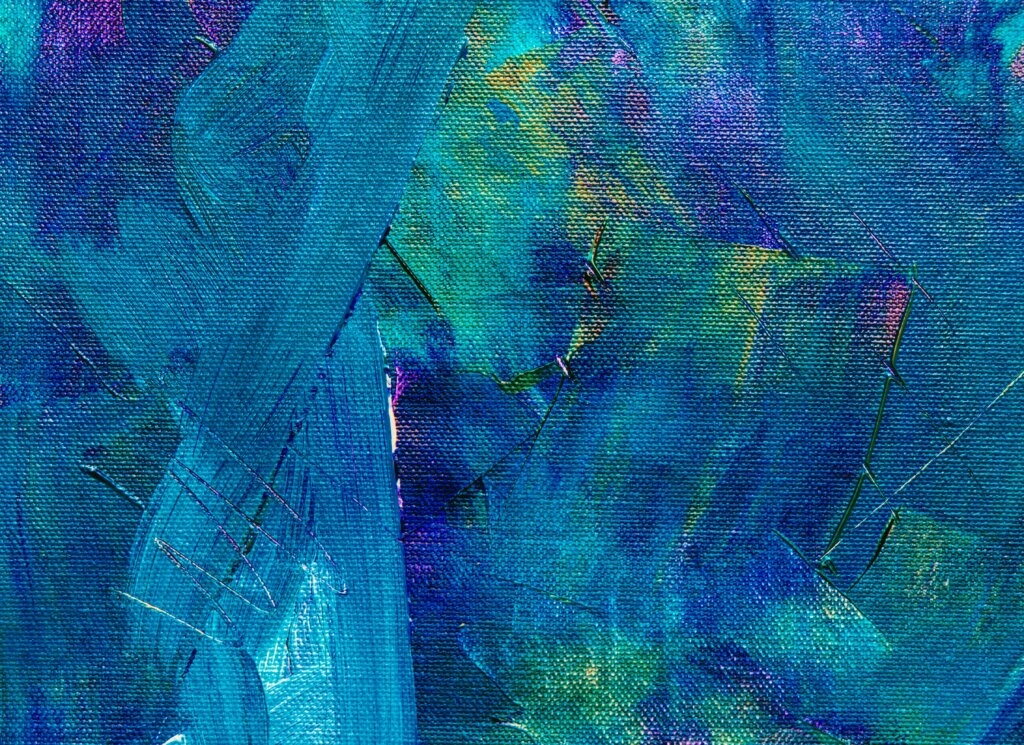
縁は一因果の継続中に他因果の継続が竄入し来るもの、
無数の因果(原因と結果)は交叉していると、ここでは言われています。
つまり、ある原因が結果をもたらす過程と別の原因が結果をもたらす過程がある一点でクロスすると熊楠は考えます。
クロスしたとしても互いに影響を与えない場合が「縁」であると彼は分析します。
一方で、影響する場合もあり、その場合が「起」であると言うのです。
それが多少の影響を加えるときは起、
次のような具体例を出しています。
縁の場合
熊楠が那智山に登り、小学校教員に会う。別に何が起こるということもなかった。
起の場合
その人(小学校教員)と話して、実は教員が古の撃剣の師匠である人の娘婿であると知って、明日師匠を尋ねてみようと思い、尋ねてみる。
因果が溢れている
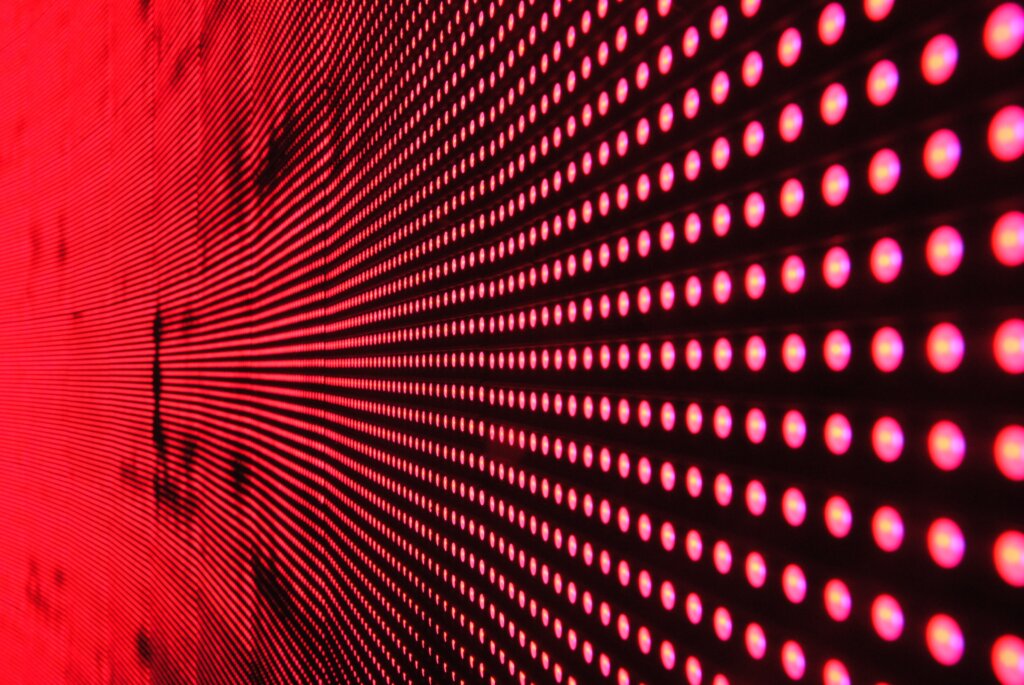
故にわれわれは諸多の因果をこの身に継続しおる。
生きる(生活する)とは、因果の網の目の中で暮らすことと同義であるのでしょう。
縁に至りては一瞬に無数にあう。
私たちは、多くの場合、縁を意識することなく毎日を送っています。
無数の縁を私たちはシャワーのように浴びて、数多の縁が通り過ぎていくのでしょう。
それが心のとめよう、体のとめようで事をおこし(起)、それにより今まで続けて来れる因果の行動が、軌道をはずれてゆき、またはずれた物が、軌道に復しゆくなり。
縁が起に変わるのかいなかは、心の感じ方、身体の受け止め方にかかっているのでしょう。
その小さな動き(働きかけ)次第で、因から果へのプロセスは微妙な、あるいは決定的な影響を受けて、果が異なってしまうこともあるのです。
未来に続く因果論・縁起論

出会いは無数にあり、生の瞬間瞬間が因果で満たされています。
それが起となるのは、偶然の作用というよりも、自分自身の働きかけ(受け止め方)ひとつであるのでしょう。
世に蔓延る因果論が決定論的・運命論的であり、窮屈な主張が大半であることを念頭に置くならば、熊楠の思考がいかに自由で、能動的であるかがわかるはずです。
あなたの未来はあなたの思いとは決して無縁ではありません。















